- Teks
- Sejarah
「終わったようですね」 わずかな静寂と、その後の一際大きな爆発。木々を
「終わったようですね」
わずかな静寂と、その後の一際大きな爆発。木々をなぎ倒し、森を横断するのではないかという勢いで突き進んだ衝撃波が止む。
シュニーだけでなく、丘の上にいた誰もが勝負の決着を悟っていた。
『…………』
高いステータスを誇るウォルフガングやカゲロウも、何も言わない。否、言えない。全身の毛を逆立てながら警戒するのも当然だ。
最後の一撃。そのあまりにも強大な圧力に言葉を失っているのだ。誰が放ったのかはわかっているが、それでも楽観できないほどの力の波動。戦わずして敗北を悟らせる、覇者としての存在を感じずにはいられない。
出会ってから日の浅い者からすれば、普段のシンという人物からは想像もできない荒々しい気配に皆息をのんでいた。
だからだろう。沈黙の只中にあってシュニーだけが平然としていた。
「いつまでも呆けているわけにはいきませんよ」
『ッ!?』
その一言で、一同がハッと我に返る。自らの王が最期を遂げたのだ。呆けている時間などあるはずがない。
「誰か、こっちに来る」
「あれはおそらく……」
慌てて周囲に気を張れば、自分たちの方へと近づいてくる者がいることにウォルフガングとクオーレが気づく。いつの間に接近していたのか、丘の下にその姿があった。
現れた影は一つ。何かを背負ったまま丘の上に向かって歩いてくる。言うまでもなく、シンとジラートだ。眠るように目を閉じたジラートをシンが背負っていた。
到着を待たず、皆が丘を下る。
「シン、その服……」
「ああ、ジラートにな」
裂け目の入ったコートを見て心配そうにティエラが言うが、シンの仕草に深刻なダメージはないと分かり、ほっとしたようにうなずいていた。
「馬車を出す。ジラートを頼む」
『承知』
アイテムボックスを操作するためにジラートの遺体をヴァンとラジムに任せる。馬車を取り出した後は荷台後方に寝かせ、動かないようにする。
「ジラート様……」
横たえられた遺体を見て、クオーレが湿った声をもらす。力なく肩を落とし、いつもはピンと張った耳も今はペタリと頭に張り付いていた。態度にこそ現れていないが、ウォルフガングもどこか意気消沈した様子だ。
たとえ本人が望んだ最後だったとしても、残されるものが抱く悲しみだけはどうにもならない。
「顔をあげろよ。おまえら」
そんな2人にシンは声をかける。今までとは違う。どこか威厳のある声で。
「シン殿?」
「おまえ達の王はたしかに俺に、ハイヒューマンに牙を届かせた。あいつはたしかに俺たちと同じ領域に至ったんだ」
それはこの世界に生きる者にとって不可能と同義。
限界のその果て。決して辿り着けぬと言われる境地。
戦いを生業にするものならば、一度は夢見る至高の頂。
「誇れ! たたえろ! おまえ達の王は頂へと至った戦士だ。泣くのなら、自分の責務を果たしてからにしろ!!」
悲しんでもいい。泣いてもいい。だが、それは今ではない。
ウォルフガングはこれからジラートの死を国に、民に伝えなければならない。葬儀も大々的なものになるだろう。クオーレとて現獣王の娘としての役目がある。
一度悲しみに沈めば、立ち上がるのは容易ではない。当事者にとって、相手が心深くにいればいるほどその身を苛むのだ。
大切な人を失う痛みも苦しみも、喪失感もシンは知っている。
だからこそ、言う。今はまだ、その時ではないと。今はジラートの生きざまをたたえ、送り出す時だと。
「ジラートなら、そう言うぜ?」
「……シン、殿……」
「お心遣い、痛み入る」
酷なことを言っているという自覚はある。感謝されるようなことではない。それでも、ここは自分が言うべきだと思ったのだ。
「お嬢も、ウルもそう気を落とすな。王の顔を見てみろ」
顔をあげた2人に今度はヴァンが声をかける。余談だが、ウルというのは親しいものがウォルフガングを呼ぶ時の名称らしい。
「満足したという顔をしておる。これを見て未練が残ったなどとは誰も思うまい」
ラジムもまた、2人を元気づけるために声をかける。ラジムの言うとおり、ジラートの顔には仄かな笑みが浮かんでいた。長い時間を共にしたヴァンとラジムには、ジラートが何を思って逝ったのか考えるまでもなく理解できた。
悲しいという感情はたしかにある。しかし、それ以上に安堵の気持ちが強かった。ジラートが体のことを隠していたのは知っていた。だからこそ、未練を残したまま逝かずにすんだ喜びの方が大きかったのだ。
おめおめと生き長らえるくらいなら、思うがままに戦い死ぬ。それが戦士として生きてきた者の生き様なのだから。
「そう、ね。めそめそしてたら、笑われちゃう」
「ああ、そうだな」
最もジラートの近くにいた2人の言葉に、クオーレとウォルフガングも自分を取り戻したようだ。人によってはそれでも生きていてほしかったなどという場面ではあるが、ジラートの教えを受けてきた2人はそうは思わなかったらしい。2人からはしっかりとジラートの死と向き合い、踏み出す決意が見て取れた。
◆◆◆◆
さほど時間をかけずに馬車は屋敷へと到着した。
ヴァンとラジムによって遺体は運び出され、ウォルフガングの指示で各部署の責任者や幹部達が集められる。ジラートの死が告げられると驚く者、悲しむ者、どこか安堵の表情を見せる者など反応は様々だった。
ラルア大森林で何か起こっていることは、察していた者もいたようだ。どうやらファルニッドまで戦いの音が響いていたらしい。それとジラートの死をつなぎ合わせ、誰と戦ったのだと言う者までいた。
「初代の最後に、相応しいお方だ」
ウォルフガングはシンの名前は告げなかった。ただ、ジラートの最後の戦いにこれ以上の適役はいないと、はっきりと宣言した。
それは誰なのかと訝しむ者も当然いたが、大半の者が同じハイヒューマン配下の内の誰かだろうとあたりをつけた。シュニーとシュバイドの両名とはよくやり取りをしていたのは周囲もよく知っていたし、それ以外のメンバーも実力に疑いはない。
まだ納得のいっていなかった者達も、実際にジラートの遺体と対面してその死に顔を見るとウォルフガングの言葉が正しいものだと理解した。これは武人気質の者が多いファルニッドだからこその反応だろう。
全員が納得してからのことは、とにかく早かった。その日のうちに犬族以外の各コミュニティーに連絡を飛ばし、一致団結して葬儀の準備に取り掛かっていく。
隠居していたとしてもジラートは紛れもない建国の父。国を挙げての大々的な葬儀となるのは必然だった。1週間もしないうちに様々な人が、物がファルニッドへと集まり、葬儀というよりはお祭り騒ぎのようになっていたのはきっと気にしてはいけないところなのだろう。ファルニッドの部族以外にも国交のある国からも使者が来ているようだ。
シン達は葬儀の準備ができるまでとくにやることもないので、資料館へと通う日々を過ごしていた。やはりというべきか、成果は芳しくない。それでも許可がなければ入れないゾーンに入れた分、ベイルリヒトの一般人エリアの本よりは有用なものをいくつか見つけられていた。
そして、ジラートの死から10日後。ファルニッド獣連合犬族の首都エリデンにて、初代獣王・ジラート・エストレアの葬儀が行われた。
シンとシュニーも参加している。シュニーはジラートの死の報を聞いてきたと言えば、何の疑いもなく受け入れられた。シンはシュニーとは別枠で、全身鎧フルプレートを装備してジラートを見送る列に並んでいる。参列者の中には戦場を共にした装備を身に付けてきている者も多く、歴戦の勇士と見紛う鎧を着たシンもさぞかし有名な戦士なのだろうと思われていた。ジラートの戦歴は長く、戦場を共にした者同士でも顔見知りでない者というのが意外と多いのだ。
葬儀には国の上層部の面々、各部族の長やその息子、引退した元将軍など凄まじいメンツがそろっていた。中にはエルフやピクシーの集落からの代表までいる。最前列には王であるウォルフガングと娘のクオーレ。その隣にはシュニーともう一人。ファルニッドの同盟国である竜皇国・キルモントの代表としてシンのサポートキャラクターNo.4のシュバイド・エトラックがいた。
黒曜石のような鱗と赤い瞳のハイドラグニル。国を作った者、ともにシンのパーティで前衛を務めた者として一番交流があったとシンは聞いていた。両国の首都はかなりの距離があるはずだったがどうやら間に合ったらしい。
葬儀は粛々と進み、トラブル一つなく静かに終了した。ジラートの遺体は歴代の王が眠る地へと埋葬されるらしい。大地に生まれ、大地に生かされ、大地に帰る。それが、ビーストの多くが持つ死生観だった。
式典の最後、狼型タイプ・ウルフ、犬型タイプ・ドッグ、狐型タイプ・フォックスなどのビーストが一斉に遠吠えを行う。最後まで戦い抜いた戦士を送る、葬送の調べだ。
多くの人々に見送られる中、ジラートの遺体は王の墓へと埋葬された。
◆◆◆◆
葬儀が終わると、シンは屋敷に戻る。ウォルフガングや国の幹部達は、これからのことで話し合わなければならないことが山積みらしく、まだしばらく帰れないようだ。
「隣りに座ってもよろしいですかな?」
膝の上のユズハを撫でながらぼーっと庭を見ていたシンに声をかけてきたのは、ヴァンだった。後ろにはラジムの姿も見える。
「話し合いはいいのか?」
「我らのような老兵に出番などありませぬ」
「さよう、国のことはすでに他のものに任せてありますゆえ」
シンを挟むように縁側に腰かけ、ヴァンは言う。そして、その言葉に同意するラジム。
2人の纏う雰囲気は穏やかで、シンには今にも消えてしまいそうに感じられた。
「おまえ達はこれからどうするんだ?」
「旅に、でようかと」
「旅?」
「はい、仲間も待っておりますゆえ」
「……そうか。仲良くやれよ」
仲間も待っている。ヴァンの言った言葉と纏った雰囲気に、シンは単調な言葉しかでない。2人のいく先がわかってしまう。
「……なぁ、2人から見てジラートはどんな奴だった?」
数分の沈黙の後、シンの口から出たのはそんな言葉だった。
「偉大なお方でした」
「比肩する者のない戦士でした」
ヴァンとラジムは懐かしむように目を閉じて言う。
誰よりも先に先頭に立ち、道を指し示す先導者。圧倒的な戦闘力を有する、英雄。
「孤独なお方でした」
「寂しがり屋な方でした」
並び立つ者のいない勇者。孤独な王。
その戦闘力ゆえに、戦場では1人で戦わざるを得ないことが多かったという。シュニーやシュバイドがいなければ本当に1人で戦場に立ち続けただろうと2人は言う。そのくせ、やたらと仲間に絡んだらしい。
「仲間思いのお方でした」
「戦うことしかできない方でした」
だからこそ、ジラートの周りには人が集まった。仲間のために武器をとり、襲いかかるモンスターを打ち倒し、地殻変動の混乱の中で部族をまとめていく。まるで、おとぎ話の英雄のように。
ただ、数多ある英雄譚と違ったのは本人に王をやる気がなかったことだ。ジラートは純粋な戦闘職。それ以外はからっきしだった。
民衆はジラートを求めるが、ジラートは本人が自覚するほどに統治能力がなかった。どちらかと言えば将軍職の方があっていたのだ。おかげで、支える立場となった者達――ヴァンとラジムはその筆頭だ――も苦労したという。なのに誰もやめようとしなかったあたりが、周りとの信頼関係を感じさせる。
異常ともいえるような戦闘力をもちながら、孤立することがなかったのはきっとそのおかげ。戦場と日常のギャップが凄まじかったと最後に2人は口をそろえた。
「そうか、教えてくれてありがとな」
シンの知らないジラートの姿がそこにあった。
「シン殿、あらためて礼を言わせていただきたい」
「なんだ、突然」
ジラートのことを話していたヴァンが、姿勢を正してシンに頭を下げてくる。視線を移せば、ラジムもまた、同じように頭を下げていた。
「おい、2人とも」
「我らが王の願い、叶えてくださったこと。感謝の念がつきませぬ」
「よしてくれ。本当にたまたまなんだ」
そ
わずかな静寂と、その後の一際大きな爆発。木々をなぎ倒し、森を横断するのではないかという勢いで突き進んだ衝撃波が止む。
シュニーだけでなく、丘の上にいた誰もが勝負の決着を悟っていた。
『…………』
高いステータスを誇るウォルフガングやカゲロウも、何も言わない。否、言えない。全身の毛を逆立てながら警戒するのも当然だ。
最後の一撃。そのあまりにも強大な圧力に言葉を失っているのだ。誰が放ったのかはわかっているが、それでも楽観できないほどの力の波動。戦わずして敗北を悟らせる、覇者としての存在を感じずにはいられない。
出会ってから日の浅い者からすれば、普段のシンという人物からは想像もできない荒々しい気配に皆息をのんでいた。
だからだろう。沈黙の只中にあってシュニーだけが平然としていた。
「いつまでも呆けているわけにはいきませんよ」
『ッ!?』
その一言で、一同がハッと我に返る。自らの王が最期を遂げたのだ。呆けている時間などあるはずがない。
「誰か、こっちに来る」
「あれはおそらく……」
慌てて周囲に気を張れば、自分たちの方へと近づいてくる者がいることにウォルフガングとクオーレが気づく。いつの間に接近していたのか、丘の下にその姿があった。
現れた影は一つ。何かを背負ったまま丘の上に向かって歩いてくる。言うまでもなく、シンとジラートだ。眠るように目を閉じたジラートをシンが背負っていた。
到着を待たず、皆が丘を下る。
「シン、その服……」
「ああ、ジラートにな」
裂け目の入ったコートを見て心配そうにティエラが言うが、シンの仕草に深刻なダメージはないと分かり、ほっとしたようにうなずいていた。
「馬車を出す。ジラートを頼む」
『承知』
アイテムボックスを操作するためにジラートの遺体をヴァンとラジムに任せる。馬車を取り出した後は荷台後方に寝かせ、動かないようにする。
「ジラート様……」
横たえられた遺体を見て、クオーレが湿った声をもらす。力なく肩を落とし、いつもはピンと張った耳も今はペタリと頭に張り付いていた。態度にこそ現れていないが、ウォルフガングもどこか意気消沈した様子だ。
たとえ本人が望んだ最後だったとしても、残されるものが抱く悲しみだけはどうにもならない。
「顔をあげろよ。おまえら」
そんな2人にシンは声をかける。今までとは違う。どこか威厳のある声で。
「シン殿?」
「おまえ達の王はたしかに俺に、ハイヒューマンに牙を届かせた。あいつはたしかに俺たちと同じ領域に至ったんだ」
それはこの世界に生きる者にとって不可能と同義。
限界のその果て。決して辿り着けぬと言われる境地。
戦いを生業にするものならば、一度は夢見る至高の頂。
「誇れ! たたえろ! おまえ達の王は頂へと至った戦士だ。泣くのなら、自分の責務を果たしてからにしろ!!」
悲しんでもいい。泣いてもいい。だが、それは今ではない。
ウォルフガングはこれからジラートの死を国に、民に伝えなければならない。葬儀も大々的なものになるだろう。クオーレとて現獣王の娘としての役目がある。
一度悲しみに沈めば、立ち上がるのは容易ではない。当事者にとって、相手が心深くにいればいるほどその身を苛むのだ。
大切な人を失う痛みも苦しみも、喪失感もシンは知っている。
だからこそ、言う。今はまだ、その時ではないと。今はジラートの生きざまをたたえ、送り出す時だと。
「ジラートなら、そう言うぜ?」
「……シン、殿……」
「お心遣い、痛み入る」
酷なことを言っているという自覚はある。感謝されるようなことではない。それでも、ここは自分が言うべきだと思ったのだ。
「お嬢も、ウルもそう気を落とすな。王の顔を見てみろ」
顔をあげた2人に今度はヴァンが声をかける。余談だが、ウルというのは親しいものがウォルフガングを呼ぶ時の名称らしい。
「満足したという顔をしておる。これを見て未練が残ったなどとは誰も思うまい」
ラジムもまた、2人を元気づけるために声をかける。ラジムの言うとおり、ジラートの顔には仄かな笑みが浮かんでいた。長い時間を共にしたヴァンとラジムには、ジラートが何を思って逝ったのか考えるまでもなく理解できた。
悲しいという感情はたしかにある。しかし、それ以上に安堵の気持ちが強かった。ジラートが体のことを隠していたのは知っていた。だからこそ、未練を残したまま逝かずにすんだ喜びの方が大きかったのだ。
おめおめと生き長らえるくらいなら、思うがままに戦い死ぬ。それが戦士として生きてきた者の生き様なのだから。
「そう、ね。めそめそしてたら、笑われちゃう」
「ああ、そうだな」
最もジラートの近くにいた2人の言葉に、クオーレとウォルフガングも自分を取り戻したようだ。人によってはそれでも生きていてほしかったなどという場面ではあるが、ジラートの教えを受けてきた2人はそうは思わなかったらしい。2人からはしっかりとジラートの死と向き合い、踏み出す決意が見て取れた。
◆◆◆◆
さほど時間をかけずに馬車は屋敷へと到着した。
ヴァンとラジムによって遺体は運び出され、ウォルフガングの指示で各部署の責任者や幹部達が集められる。ジラートの死が告げられると驚く者、悲しむ者、どこか安堵の表情を見せる者など反応は様々だった。
ラルア大森林で何か起こっていることは、察していた者もいたようだ。どうやらファルニッドまで戦いの音が響いていたらしい。それとジラートの死をつなぎ合わせ、誰と戦ったのだと言う者までいた。
「初代の最後に、相応しいお方だ」
ウォルフガングはシンの名前は告げなかった。ただ、ジラートの最後の戦いにこれ以上の適役はいないと、はっきりと宣言した。
それは誰なのかと訝しむ者も当然いたが、大半の者が同じハイヒューマン配下の内の誰かだろうとあたりをつけた。シュニーとシュバイドの両名とはよくやり取りをしていたのは周囲もよく知っていたし、それ以外のメンバーも実力に疑いはない。
まだ納得のいっていなかった者達も、実際にジラートの遺体と対面してその死に顔を見るとウォルフガングの言葉が正しいものだと理解した。これは武人気質の者が多いファルニッドだからこその反応だろう。
全員が納得してからのことは、とにかく早かった。その日のうちに犬族以外の各コミュニティーに連絡を飛ばし、一致団結して葬儀の準備に取り掛かっていく。
隠居していたとしてもジラートは紛れもない建国の父。国を挙げての大々的な葬儀となるのは必然だった。1週間もしないうちに様々な人が、物がファルニッドへと集まり、葬儀というよりはお祭り騒ぎのようになっていたのはきっと気にしてはいけないところなのだろう。ファルニッドの部族以外にも国交のある国からも使者が来ているようだ。
シン達は葬儀の準備ができるまでとくにやることもないので、資料館へと通う日々を過ごしていた。やはりというべきか、成果は芳しくない。それでも許可がなければ入れないゾーンに入れた分、ベイルリヒトの一般人エリアの本よりは有用なものをいくつか見つけられていた。
そして、ジラートの死から10日後。ファルニッド獣連合犬族の首都エリデンにて、初代獣王・ジラート・エストレアの葬儀が行われた。
シンとシュニーも参加している。シュニーはジラートの死の報を聞いてきたと言えば、何の疑いもなく受け入れられた。シンはシュニーとは別枠で、全身鎧フルプレートを装備してジラートを見送る列に並んでいる。参列者の中には戦場を共にした装備を身に付けてきている者も多く、歴戦の勇士と見紛う鎧を着たシンもさぞかし有名な戦士なのだろうと思われていた。ジラートの戦歴は長く、戦場を共にした者同士でも顔見知りでない者というのが意外と多いのだ。
葬儀には国の上層部の面々、各部族の長やその息子、引退した元将軍など凄まじいメンツがそろっていた。中にはエルフやピクシーの集落からの代表までいる。最前列には王であるウォルフガングと娘のクオーレ。その隣にはシュニーともう一人。ファルニッドの同盟国である竜皇国・キルモントの代表としてシンのサポートキャラクターNo.4のシュバイド・エトラックがいた。
黒曜石のような鱗と赤い瞳のハイドラグニル。国を作った者、ともにシンのパーティで前衛を務めた者として一番交流があったとシンは聞いていた。両国の首都はかなりの距離があるはずだったがどうやら間に合ったらしい。
葬儀は粛々と進み、トラブル一つなく静かに終了した。ジラートの遺体は歴代の王が眠る地へと埋葬されるらしい。大地に生まれ、大地に生かされ、大地に帰る。それが、ビーストの多くが持つ死生観だった。
式典の最後、狼型タイプ・ウルフ、犬型タイプ・ドッグ、狐型タイプ・フォックスなどのビーストが一斉に遠吠えを行う。最後まで戦い抜いた戦士を送る、葬送の調べだ。
多くの人々に見送られる中、ジラートの遺体は王の墓へと埋葬された。
◆◆◆◆
葬儀が終わると、シンは屋敷に戻る。ウォルフガングや国の幹部達は、これからのことで話し合わなければならないことが山積みらしく、まだしばらく帰れないようだ。
「隣りに座ってもよろしいですかな?」
膝の上のユズハを撫でながらぼーっと庭を見ていたシンに声をかけてきたのは、ヴァンだった。後ろにはラジムの姿も見える。
「話し合いはいいのか?」
「我らのような老兵に出番などありませぬ」
「さよう、国のことはすでに他のものに任せてありますゆえ」
シンを挟むように縁側に腰かけ、ヴァンは言う。そして、その言葉に同意するラジム。
2人の纏う雰囲気は穏やかで、シンには今にも消えてしまいそうに感じられた。
「おまえ達はこれからどうするんだ?」
「旅に、でようかと」
「旅?」
「はい、仲間も待っておりますゆえ」
「……そうか。仲良くやれよ」
仲間も待っている。ヴァンの言った言葉と纏った雰囲気に、シンは単調な言葉しかでない。2人のいく先がわかってしまう。
「……なぁ、2人から見てジラートはどんな奴だった?」
数分の沈黙の後、シンの口から出たのはそんな言葉だった。
「偉大なお方でした」
「比肩する者のない戦士でした」
ヴァンとラジムは懐かしむように目を閉じて言う。
誰よりも先に先頭に立ち、道を指し示す先導者。圧倒的な戦闘力を有する、英雄。
「孤独なお方でした」
「寂しがり屋な方でした」
並び立つ者のいない勇者。孤独な王。
その戦闘力ゆえに、戦場では1人で戦わざるを得ないことが多かったという。シュニーやシュバイドがいなければ本当に1人で戦場に立ち続けただろうと2人は言う。そのくせ、やたらと仲間に絡んだらしい。
「仲間思いのお方でした」
「戦うことしかできない方でした」
だからこそ、ジラートの周りには人が集まった。仲間のために武器をとり、襲いかかるモンスターを打ち倒し、地殻変動の混乱の中で部族をまとめていく。まるで、おとぎ話の英雄のように。
ただ、数多ある英雄譚と違ったのは本人に王をやる気がなかったことだ。ジラートは純粋な戦闘職。それ以外はからっきしだった。
民衆はジラートを求めるが、ジラートは本人が自覚するほどに統治能力がなかった。どちらかと言えば将軍職の方があっていたのだ。おかげで、支える立場となった者達――ヴァンとラジムはその筆頭だ――も苦労したという。なのに誰もやめようとしなかったあたりが、周りとの信頼関係を感じさせる。
異常ともいえるような戦闘力をもちながら、孤立することがなかったのはきっとそのおかげ。戦場と日常のギャップが凄まじかったと最後に2人は口をそろえた。
「そうか、教えてくれてありがとな」
シンの知らないジラートの姿がそこにあった。
「シン殿、あらためて礼を言わせていただきたい」
「なんだ、突然」
ジラートのことを話していたヴァンが、姿勢を正してシンに頭を下げてくる。視線を移せば、ラジムもまた、同じように頭を下げていた。
「おい、2人とも」
「我らが王の願い、叶えてくださったこと。感謝の念がつきませぬ」
「よしてくれ。本当にたまたまなんだ」
そ
0/5000
「終わったようですね」 わずかな静寂と、その後の一際大きな爆発。木々をなぎ倒し、森を横断するのではないかという勢いで突き進んだ衝撃波が止む。 シュニーだけでなく、丘の上にいた誰もが勝負の決着を悟っていた。『…………』 高いステータスを誇るウォルフガングやカゲロウも、何も言わない。否、言えない。全身の毛を逆立てながら警戒するのも当然だ。 最後の一撃。そのあまりにも強大な圧力に言葉を失っているのだ。誰が放ったのかはわかっているが、それでも楽観できないほどの力の波動。戦わずして敗北を悟らせる、覇者としての存在を感じずにはいられない。 出会ってから日の浅い者からすれば、普段のシンという人物からは想像もできない荒々しい気配に皆息をのんでいた。 だからだろう。沈黙の只中にあってシュニーだけが平然としていた。「いつまでも呆けているわけにはいきませんよ」『ッ!?』 その一言で、一同がハッと我に返る。自らの王が最期を遂げたのだ。呆けている時間などあるはずがない。「誰か、こっちに来る」「あれはおそらく……」 慌てて周囲に気を張れば、自分たちの方へと近づいてくる者がいることにウォルフガングとクオーレが気づく。いつの間に接近していたのか、丘の下にその姿があった。 現れた影は一つ。何かを背負ったまま丘の上に向かって歩いてくる。言うまでもなく、シンとジラートだ。眠るように目を閉じたジラートをシンが背負っていた。 到着を待たず、皆が丘を下る。「シン、その服……」「ああ、ジラートにな」 裂け目の入ったコートを見て心配そうにティエラが言うが、シンの仕草に深刻なダメージはないと分かり、ほっとしたようにうなずいていた。「馬車を出す。ジラートを頼む」『承知』 アイテムボックスを操作するためにジラートの遺体をヴァンとラジムに任せる。馬車を取り出した後は荷台後方に寝かせ、動かないようにする。「ジラート様……」 横たえられた遺体を見て、クオーレが湿った声をもらす。力なく肩を落とし、いつもはピンと張った耳も今はペタリと頭に張り付いていた。態度にこそ現れていないが、ウォルフガングもどこか意気消沈した様子だ。 たとえ本人が望んだ最後だったとしても、残されるものが抱く悲しみだけはどうにもならない。「顔をあげろよ。おまえら」 そんな2人にシンは声をかける。今までとは違う。どこか威厳のある声で。「シン殿?」「おまえ達の王はたしかに俺に、ハイヒューマンに牙を届かせた。あいつはたしかに俺たちと同じ領域に至ったんだ」 それはこの世界に生きる者にとって不可能と同義。 限界のその果て。決して辿り着けぬと言われる境地。 戦いを生業にするものならば、一度は夢見る至高の頂。「誇れ! たたえろ! おまえ達の王は頂へと至った戦士だ。泣くのなら、自分の責務を果たしてからにしろ!!」 悲しんでもいい。泣いてもいい。だが、それは今ではない。 ウォルフガングはこれからジラートの死を国に、民に伝えなければならない。葬儀も大々的なものになるだろう。クオーレとて現獣王の娘としての役目がある。 一度悲しみに沈めば、立ち上がるのは容易ではない。当事者にとって、相手が心深くにいればいるほどその身を苛むのだ。 大切な人を失う痛みも苦しみも、喪失感もシンは知っている。 だからこそ、言う。今はまだ、その時ではないと。今はジラートの生きざまをたたえ、送り出す時だと。「ジラートなら、そう言うぜ?」「……シン、殿……」「お心遣い、痛み入る」 酷なことを言っているという自覚はある。感謝されるようなことではない。それでも、ここは自分が言うべきだと思ったのだ。「お嬢も、ウルもそう気を落とすな。王の顔を見てみろ」 顔をあげた2人に今度はヴァンが声をかける。余談だが、ウルというのは親しいものがウォルフガングを呼ぶ時の名称らしい。「満足したという顔をしておる。これを見て未練が残ったなどとは誰も思うまい」 ラジムもまた、2人を元気づけるために声をかける。ラジムの言うとおり、ジラートの顔には仄かな笑みが浮かんでいた。長い時間を共にしたヴァンとラジムには、ジラートが何を思って逝ったのか考えるまでもなく理解できた。 悲しいという感情はたしかにある。しかし、それ以上に安堵の気持ちが強かった。ジラートが体のことを隠していたのは知っていた。だからこそ、未練を残したまま逝かずにすんだ喜びの方が大きかったのだ。 おめおめと生き長らえるくらいなら、思うがままに戦い死ぬ。それが戦士として生きてきた者の生き様なのだから。「そう、ね。めそめそしてたら、笑われちゃう」「ああ、そうだな」 最もジラートの近くにいた2人の言葉に、クオーレとウォルフガングも自分を取り戻したようだ。人によってはそれでも生きていてほしかったなどという場面ではあるが、ジラートの教えを受けてきた2人はそうは思わなかったらしい。2人からはしっかりとジラートの死と向き合い、踏み出す決意が見て取れた。 ◆◆◆◆ さほど時間をかけずに馬車は屋敷へと到着した。 ヴァンとラジムによって遺体は運び出され、ウォルフガングの指示で各部署の責任者や幹部達が集められる。ジラートの死が告げられると驚く者、悲しむ者、どこか安堵の表情を見せる者など反応は様々だった。 ラルア大森林で何か起こっていることは、察していた者もいたようだ。どうやらファルニッドまで戦いの音が響いていたらしい。それとジラートの死をつなぎ合わせ、誰と戦ったのだと言う者までいた。「初代の最後に、相応しいお方だ」 ウォルフガングはシンの名前は告げなかった。ただ、ジラートの最後の戦いにこれ以上の適役はいないと、はっきりと宣言した。 それは誰なのかと訝しむ者も当然いたが、大半の者が同じハイヒューマン配下の内の誰かだろうとあたりをつけた。シュニーとシュバイドの両名とはよくやり取りをしていたのは周囲もよく知っていたし、それ以外のメンバーも実力に疑いはない。 まだ納得のいっていなかった者達も、実際にジラートの遺体と対面してその死に顔を見るとウォルフガングの言葉が正しいものだと理解した。これは武人気質の者が多いファルニッドだからこその反応だろう。
全員が納得してからのことは、とにかく早かった。その日のうちに犬族以外の各コミュニティーに連絡を飛ばし、一致団結して葬儀の準備に取り掛かっていく。
隠居していたとしてもジラートは紛れもない建国の父。国を挙げての大々的な葬儀となるのは必然だった。1週間もしないうちに様々な人が、物がファルニッドへと集まり、葬儀というよりはお祭り騒ぎのようになっていたのはきっと気にしてはいけないところなのだろう。ファルニッドの部族以外にも国交のある国からも使者が来ているようだ。
シン達は葬儀の準備ができるまでとくにやることもないので、資料館へと通う日々を過ごしていた。やはりというべきか、成果は芳しくない。それでも許可がなければ入れないゾーンに入れた分、ベイルリヒトの一般人エリアの本よりは有用なものをいくつか見つけられていた。
そして、ジラートの死から10日後。ファルニッド獣連合犬族の首都エリデンにて、初代獣王・ジラート・エストレアの葬儀が行われた。
シンとシュニーも参加している。シュニーはジラートの死の報を聞いてきたと言えば、何の疑いもなく受け入れられた。シンはシュニーとは別枠で、全身鎧フルプレートを装備してジラートを見送る列に並んでいる。参列者の中には戦場を共にした装備を身に付けてきている者も多く、歴戦の勇士と見紛う鎧を着たシンもさぞかし有名な戦士なのだろうと思われていた。ジラートの戦歴は長く、戦場を共にした者同士でも顔見知りでない者というのが意外と多いのだ。
葬儀には国の上層部の面々、各部族の長やその息子、引退した元将軍など凄まじいメンツがそろっていた。中にはエルフやピクシーの集落からの代表までいる。最前列には王であるウォルフガングと娘のクオーレ。その隣にはシュニーともう一人。ファルニッドの同盟国である竜皇国・キルモントの代表としてシンのサポートキャラクターNo.4のシュバイド・エトラックがいた。
黒曜石のような鱗と赤い瞳のハイドラグニル。国を作った者、ともにシンのパーティで前衛を務めた者として一番交流があったとシンは聞いていた。両国の首都はかなりの距離があるはずだったがどうやら間に合ったらしい。
葬儀は粛々と進み、トラブル一つなく静かに終了した。ジラートの遺体は歴代の王が眠る地へと埋葬されるらしい。大地に生まれ、大地に生かされ、大地に帰る。それが、ビーストの多くが持つ死生観だった。
式典の最後、狼型タイプ・ウルフ、犬型タイプ・ドッグ、狐型タイプ・フォックスなどのビーストが一斉に遠吠えを行う。最後まで戦い抜いた戦士を送る、葬送の調べだ。
多くの人々に見送られる中、ジラートの遺体は王の墓へと埋葬された。
◆◆◆◆
葬儀が終わると、シンは屋敷に戻る。ウォルフガングや国の幹部達は、これからのことで話し合わなければならないことが山積みらしく、まだしばらく帰れないようだ。
「隣りに座ってもよろしいですかな?」
膝の上のユズハを撫でながらぼーっと庭を見ていたシンに声をかけてきたのは、ヴァンだった。後ろにはラジムの姿も見える。
「話し合いはいいのか?」
「我らのような老兵に出番などありませぬ」
「さよう、国のことはすでに他のものに任せてありますゆえ」
シンを挟むように縁側に腰かけ、ヴァンは言う。そして、その言葉に同意するラジム。
2人の纏う雰囲気は穏やかで、シンには今にも消えてしまいそうに感じられた。
「おまえ達はこれからどうするんだ?」
「旅に、でようかと」
「旅?」
「はい、仲間も待っておりますゆえ」
「……そうか。仲良くやれよ」
仲間も待っている。ヴァンの言った言葉と纏った雰囲気に、シンは単調な言葉しかでない。2人のいく先がわかってしまう。
「……なぁ、2人から見てジラートはどんな奴だった?」
数分の沈黙の後、シンの口から出たのはそんな言葉だった。
「偉大なお方でした」
「比肩する者のない戦士でした」
ヴァンとラジムは懐かしむように目を閉じて言う。
誰よりも先に先頭に立ち、道を指し示す先導者。圧倒的な戦闘力を有する、英雄。
「孤独なお方でした」
「寂しがり屋な方でした」
並び立つ者のいない勇者。孤独な王。
その戦闘力ゆえに、戦場では1人で戦わざるを得ないことが多かったという。シュニーやシュバイドがいなければ本当に1人で戦場に立ち続けただろうと2人は言う。そのくせ、やたらと仲間に絡んだらしい。
「仲間思いのお方でした」
「戦うことしかできない方でした」
だからこそ、ジラートの周りには人が集まった。仲間のために武器をとり、襲いかかるモンスターを打ち倒し、地殻変動の混乱の中で部族をまとめていく。まるで、おとぎ話の英雄のように。
ただ、数多ある英雄譚と違ったのは本人に王をやる気がなかったことだ。ジラートは純粋な戦闘職。それ以外はからっきしだった。
民衆はジラートを求めるが、ジラートは本人が自覚するほどに統治能力がなかった。どちらかと言えば将軍職の方があっていたのだ。おかげで、支える立場となった者達――ヴァンとラジムはその筆頭だ――も苦労したという。なのに誰もやめようとしなかったあたりが、周りとの信頼関係を感じさせる。
異常ともいえるような戦闘力をもちながら、孤立することがなかったのはきっとそのおかげ。戦場と日常のギャップが凄まじかったと最後に2人は口をそろえた。
「そうか、教えてくれてありがとな」
シンの知らないジラートの姿がそこにあった。
「シン殿、あらためて礼を言わせていただきたい」
「なんだ、突然」
ジラートのことを話していたヴァンが、姿勢を正してシンに頭を下げてくる。視線を移せば、ラジムもまた、同じように頭を下げていた。
「おい、2人とも」
「我らが王の願い、叶えてくださったこと。感謝の念がつきませぬ」
「よしてくれ。本当にたまたまなんだ」
そ
全員が納得してからのことは、とにかく早かった。その日のうちに犬族以外の各コミュニティーに連絡を飛ばし、一致団結して葬儀の準備に取り掛かっていく。
隠居していたとしてもジラートは紛れもない建国の父。国を挙げての大々的な葬儀となるのは必然だった。1週間もしないうちに様々な人が、物がファルニッドへと集まり、葬儀というよりはお祭り騒ぎのようになっていたのはきっと気にしてはいけないところなのだろう。ファルニッドの部族以外にも国交のある国からも使者が来ているようだ。
シン達は葬儀の準備ができるまでとくにやることもないので、資料館へと通う日々を過ごしていた。やはりというべきか、成果は芳しくない。それでも許可がなければ入れないゾーンに入れた分、ベイルリヒトの一般人エリアの本よりは有用なものをいくつか見つけられていた。
そして、ジラートの死から10日後。ファルニッド獣連合犬族の首都エリデンにて、初代獣王・ジラート・エストレアの葬儀が行われた。
シンとシュニーも参加している。シュニーはジラートの死の報を聞いてきたと言えば、何の疑いもなく受け入れられた。シンはシュニーとは別枠で、全身鎧フルプレートを装備してジラートを見送る列に並んでいる。参列者の中には戦場を共にした装備を身に付けてきている者も多く、歴戦の勇士と見紛う鎧を着たシンもさぞかし有名な戦士なのだろうと思われていた。ジラートの戦歴は長く、戦場を共にした者同士でも顔見知りでない者というのが意外と多いのだ。
葬儀には国の上層部の面々、各部族の長やその息子、引退した元将軍など凄まじいメンツがそろっていた。中にはエルフやピクシーの集落からの代表までいる。最前列には王であるウォルフガングと娘のクオーレ。その隣にはシュニーともう一人。ファルニッドの同盟国である竜皇国・キルモントの代表としてシンのサポートキャラクターNo.4のシュバイド・エトラックがいた。
黒曜石のような鱗と赤い瞳のハイドラグニル。国を作った者、ともにシンのパーティで前衛を務めた者として一番交流があったとシンは聞いていた。両国の首都はかなりの距離があるはずだったがどうやら間に合ったらしい。
葬儀は粛々と進み、トラブル一つなく静かに終了した。ジラートの遺体は歴代の王が眠る地へと埋葬されるらしい。大地に生まれ、大地に生かされ、大地に帰る。それが、ビーストの多くが持つ死生観だった。
式典の最後、狼型タイプ・ウルフ、犬型タイプ・ドッグ、狐型タイプ・フォックスなどのビーストが一斉に遠吠えを行う。最後まで戦い抜いた戦士を送る、葬送の調べだ。
多くの人々に見送られる中、ジラートの遺体は王の墓へと埋葬された。
◆◆◆◆
葬儀が終わると、シンは屋敷に戻る。ウォルフガングや国の幹部達は、これからのことで話し合わなければならないことが山積みらしく、まだしばらく帰れないようだ。
「隣りに座ってもよろしいですかな?」
膝の上のユズハを撫でながらぼーっと庭を見ていたシンに声をかけてきたのは、ヴァンだった。後ろにはラジムの姿も見える。
「話し合いはいいのか?」
「我らのような老兵に出番などありませぬ」
「さよう、国のことはすでに他のものに任せてありますゆえ」
シンを挟むように縁側に腰かけ、ヴァンは言う。そして、その言葉に同意するラジム。
2人の纏う雰囲気は穏やかで、シンには今にも消えてしまいそうに感じられた。
「おまえ達はこれからどうするんだ?」
「旅に、でようかと」
「旅?」
「はい、仲間も待っておりますゆえ」
「……そうか。仲良くやれよ」
仲間も待っている。ヴァンの言った言葉と纏った雰囲気に、シンは単調な言葉しかでない。2人のいく先がわかってしまう。
「……なぁ、2人から見てジラートはどんな奴だった?」
数分の沈黙の後、シンの口から出たのはそんな言葉だった。
「偉大なお方でした」
「比肩する者のない戦士でした」
ヴァンとラジムは懐かしむように目を閉じて言う。
誰よりも先に先頭に立ち、道を指し示す先導者。圧倒的な戦闘力を有する、英雄。
「孤独なお方でした」
「寂しがり屋な方でした」
並び立つ者のいない勇者。孤独な王。
その戦闘力ゆえに、戦場では1人で戦わざるを得ないことが多かったという。シュニーやシュバイドがいなければ本当に1人で戦場に立ち続けただろうと2人は言う。そのくせ、やたらと仲間に絡んだらしい。
「仲間思いのお方でした」
「戦うことしかできない方でした」
だからこそ、ジラートの周りには人が集まった。仲間のために武器をとり、襲いかかるモンスターを打ち倒し、地殻変動の混乱の中で部族をまとめていく。まるで、おとぎ話の英雄のように。
ただ、数多ある英雄譚と違ったのは本人に王をやる気がなかったことだ。ジラートは純粋な戦闘職。それ以外はからっきしだった。
民衆はジラートを求めるが、ジラートは本人が自覚するほどに統治能力がなかった。どちらかと言えば将軍職の方があっていたのだ。おかげで、支える立場となった者達――ヴァンとラジムはその筆頭だ――も苦労したという。なのに誰もやめようとしなかったあたりが、周りとの信頼関係を感じさせる。
異常ともいえるような戦闘力をもちながら、孤立することがなかったのはきっとそのおかげ。戦場と日常のギャップが凄まじかったと最後に2人は口をそろえた。
「そうか、教えてくれてありがとな」
シンの知らないジラートの姿がそこにあった。
「シン殿、あらためて礼を言わせていただきたい」
「なんだ、突然」
ジラートのことを話していたヴァンが、姿勢を正してシンに頭を下げてくる。視線を移せば、ラジムもまた、同じように頭を下げていた。
「おい、2人とも」
「我らが王の願い、叶えてくださったこと。感謝の念がつきませぬ」
「よしてくれ。本当にたまたまなんだ」
そ
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
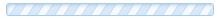
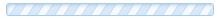
Bahasa lainnya
Dukungan alat penerjemahan: Afrikans, Albania, Amhara, Arab, Armenia, Azerbaijan, Bahasa Indonesia, Basque, Belanda, Belarussia, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Burma, Cebuano, Ceko, Chichewa, China, Cina Tradisional, Denmark, Deteksi bahasa, Esperanto, Estonia, Farsi, Finlandia, Frisia, Gaelig, Gaelik Skotlandia, Galisia, Georgia, Gujarati, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Ibrani, Igbo, Inggris, Islan, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Kannada, Katala, Kazak, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Klingon, Korea, Korsika, Kreol Haiti, Kroat, Kurdi, Laos, Latin, Latvia, Lituania, Luksemburg, Magyar, Makedonia, Malagasi, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Melayu, Mongol, Nepal, Norsk, Odia (Oriya), Pashto, Polandia, Portugis, Prancis, Punjabi, Rumania, Rusia, Samoa, Serb, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovakia, Slovenia, Somali, Spanyol, Sunda, Swahili, Swensk, Tagalog, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turki, Turkmen, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnam, Wales, Xhosa, Yiddi, Yoruba, Yunani, Zulu, Bahasa terjemahan.
- sayang jangan lupa hari ini sholat jumat
- terimakasih atas cinta yang kau berikan
- Apa arti close
- Closed
- Hari Santri Nasional memang berangkat da
- brigas
- Untuk itu, Hari Santri Nasional berpesan
- seco
- العمليات الحيوية التي يجريها الجسم
- Picks
- Please call me nakanishi
- Itulah di antara konteks yang mengilhami
- Loving can hurt, loving can hurt sometim
- what's wrong with you
- 22 Oktober dipandang layak untuk menjadi
- anjing
- banquetes
- tanggal 22 Oktober dipandang layak untuk
- Anyone can join
- tanggal 22 Oktober, dipandang layak untu
- anjing
- tanggal 22 Oktober. dipandang layak untu
- terimakasih atas cinta yang kau berikan
- Hari Santri Nasional memang berangkat da

