- Teks
- Sejarah
娘との誓い「パパー! 朝なのー! 起きるのー!」 海上の町エリセンの一
娘との誓い
「パパー! 朝なのー! 起きるのー!」
海上の町エリセンの一角、とある家の二階で幼子の声が響き渡る。時刻は、そろそろ早朝を過ぎて、日の温かみを感じ始める頃だ。窓から、本日もいい天気になることを予報するように、朝日が燦々と差し込んでいる。
ドスンッ!
「あぁ~?」
そんな朝日に照らされるベッドで爆睡しているのはハジメだ。そして、そんなハジメをパパと呼び、元気な声で起こしに来たのはミュウである。
ミュウは、ベッドの直前で重さを感じさせない見事な跳躍を決めると、そのままパパたるハジメの腹の上に十点満点の着地を決めた。もちろん、足からではない。馬乗りになる形でだ。
まだ四歳の幼子とはいえ、その体重は既に十五、六キロくらいはある。そんな重量が勢い付けて腹部に飛び乗れば、普通の人は呻き声の一つでも出そうなものだが、当然、ハジメは何の痛痒も感じていない。ただ、強制的に起こされたせいで眠たげな呻き声は出たが。
「パパ、起きるの。朝なの。おはようなの」
「……ああ、ミュウか。おはようさん。起きるからペチペチするのは止めてくれ」
ハジメが起きたことが嬉しいのか、ニコニコと笑みをこぼしながら、ミュウは、その小さなモミジのような手でハジメの頬をペチペチと叩く。ハジメは、朝の挨拶をしながら上半身を起こしミュウを抱っこすると、優しくそのエメラルドグリーンの髪を梳いてやった。気持ちよさそうに目を細めるミュウに、ハジメの頬も緩む。何処からどう見ても親子だった。
「……ん……あぅ……ハジメ? ミュウ?」
そんなほのぼのした空気の中に、突如、どこか艶めかしさを感じさせる声音が響いた。ハジメが、そちらに目を向けて少しシーツを捲ると、そこには猫のように丸めた手の甲で目元をコシコシと擦る眠たげな美少女の姿。
寝起きなのに寝癖など全くないウェーブのかかった長い金髪を、窓から差し込む朝日でキラキラと輝かせて、レッドスピネルの如き紅の瞳をシパシパとさせている。ハジメと同じく服を着ていないため、シミ一つない真っ白な肌と、前に垂れ下がった髪の隙間から見える双丘が声音と相まって美しさと共に妖艶さを感じさせた。
「どうして、パパとユエお姉ちゃんは、いつも裸なの?」
ミュウの無邪気な質問は、あくまで“朝起きるとき”という意味だ。決して二人が裸族という意味ではない。
そして、「もしかしてパジャマ持ってないの?」と不思議そうな、あるいは少し可哀想なものを見る目でハジメとユエを交互に見るミュウ。幼く純粋な質問に、「そりゃあ、お前、服は邪魔だろ?」等と、セクハラ紛いの返しなど出来るはずもなく、ハジメは、少し困った表情でユエに助けを求めた。
次第にはっきりしてきた意識で、ハジメの窮状を察したユエは、幼子の無邪気な質問に大人のテンプレで返した。
「……ミュウももっと大きくなれば分かるようになる」
「大きくなったら分かるの?」
「……ん、分かる」
首を傾げるミュウに、ゴリ押しで明確な答えを回避するユエ。ミュウの性教育は母親たるレミアにお任せだ。しかし、「う~ん」とイマイチ納得できなさそうな表情で首を傾げるミュウは、おもむろに振り返ると、とある一点を見つめながら更に無邪気な質問を繰り出して、主にハジメを追い詰めた。
「パパも、ここがおっきくなってるから分かるの? でも、ミュウにはこれないの。ミュウには分からないの?」
そう言って、朝特有の生理現象を起こしているとある場所を、ミュウはその手でペシペシと叩き始めた。大した力ではないとはいえ、デリケートな場所への衝撃にビクンッと震えたハジメは、急いでミュウを抱っこし直し、なるべく“それ”から引き離す。
「ミュウ、あれに触っちゃいけない。いいか。あれは女の子のミュウには無くて当然なんだ。気にしなくていい。あと十年、いや二十年、むしろ一生、何があっても関わっちゃいけないものだ」
至極真面目な顔で阿呆なことを語るハジメ。ミュウは、頭に“?”を浮かべつつも大好きなパパの言うことなのでコクリと素直に頷いた。それに満足気な表情をして、再度、ミュウの髪を手櫛で梳くハジメ。ミュウも、先程までの疑問は忘れたように、その優しい感触を堪能することに集中しだした。
そんなハジメに、隣のユエから何処か面白がるような眼差しが向けられる。その瞳には「過保護」とか「朝から元気」とか「朝からいっとく?」とか、そんな感じのあれこれが含まれているようだった。
それにそっぽを向くハジメ。陽の光で少しずつ暖かさを増していく中、そのほのぼのとした光景は、ミュウが中々ハジメ達を起こして来ない事に焦れたレミアや香織達がなだれ込んで来るまで続いた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ハジメ達が、【メルジーネ海底遺跡】を攻略し、潜水艇を失ったため“竜化”したティオの背に乗ってエリセンまで帰り、再び、町に話題を提供してから六日が経っていた。帰還した日から、ハジメ達は、ずっとレミアとミュウの家に世話になっている。
エリセンという町は、木で編まれた巨大な人口の浮島だ。広大な海そのものが無限の土地となっているので、町中は、通りにしろ建築物にしろ基本的にゆとりのある作りになっている。レミアとミュウの家も、二人暮らしの家にしては十分以上の大きさがあり、ハジメ達五人が寝泊りしても何の不自由も感じない程度には快適な生活空間だった。
そこでハジメ達は、手に入れた神代魔法の習熟と装備品の充実に時間をあてていた。エリセンは海鮮系料理が充実しており、波風も心地よく、中々に居心地のいい場所だったので半分はバカンス気分ではあったが。
ただ、それにしても、六日も滞在しているのは少々骨休めが過ぎると感じるところだ。その理由は、言わずもがな、ミュウである。ミュウを、この先の旅に連れて行くことは出来ない。四歳の何の力もない女の子を、東の果ての大迷宮に連れて行くなどもってのほかだ。
まして、【ハルツィナ樹海】を除く残り二つの大迷宮は更に厄介な場所にある。一つは魔人族の領土にある【シュネー雪原】の【氷結洞窟】。そしてもう一つは、何とあの【神山】なのである。どちらも、大勢力の懐に入り込まねばならないのだ。そんな場所に、ミュウを連れて行くなど絶対に出来ない。
なので、この町でお別れをしなければならないのだが、何となくそれを察しているのか、ハジメ達がその話を出そうとすると、ミュウは決まって超甘えん坊モードになり、ハジメ達に「必殺! 幼女、無言の懇願!」を発動するので中々言い出せずにいた。結局、ズルズルと神代魔法の鍛錬やら新装備の充実化やら、言い訳をしつつ六日も滞在してしまっているのである。
「それでも、いい加減出発しないとな……はぁ、ミュウに何て言うべきか……泣かれるかな。泣かれるよな……はぁ、憂鬱だ」
ハジメは、桟橋に腰掛けて“錬成”により装備やら何やらを作成しながら、憂鬱そうに独り言を呟く。奈落から出たばかりの頃は、この世界の全てをどうでもいいと思っていたのに、今や、幼子とのお別れ一つに頭を悩ませている。そんな現状に、内心、複雑な思いを抱くハジメ。
「恨むぞ、先生……」
この世界の一切合切を切り捨てて、ただ目的のためあらゆる犠牲を厭わないという考えが出来なくなったことに、そんな考えを持つに至ったきっかけたる恩師を思い出して悪態をつくハジメ。しかし、視線の先に、ユエとシア、香織、ティオ、そして彼女達と水中鬼ごっこをして戯れるミュウの溢れる笑顔を見て、言葉とは裏腹に顔には笑みが浮かんでいた。
自分には関係ないと、あの時、ミュウを見捨てていれば、あるいはアンカジを放置していれば、そしてレミアを放って置けば、さっさとミュウと分かれていれば……きっと、彼女達にあの極上の笑顔はなかっただろう。
例え切り捨てていても、ユエ達は不幸だと感じる分けでも笑顔が無くなるわけでもないだろうが、今浮かべるそれとは比べるべくもないのではないだろうか。それはきっと、ここまでのハジメのあり方が“寂しい生き方”ではなかったからに違いない。
海人族の特性を十全に発揮して、チートの権化達から華麗に逃げ回る変則的な鬼ごっこ(ミュウ以外全員鬼役)を全力で楽しんでいるミュウを見ながら、再び、溜息を吐くハジメ。そんなハジメの桟橋から投げ出した両足の間から、突然、人影がザバッと音を立てて現れた。海中から水を滴らせて現れたのは、ミュウの母親であるレミアだ。
レミアは、エメラルドグリーンの長い髪を背中で一本の緩い三つ編みにしており、ライトグリーンの結構際どいビキニを身に付けている。ミュウと再会した当初は、相当やつれていたのだが、現在は、再生魔法という反則級の回復効果により以前の健康体を完全に取り戻しており、一児の母とは思えない、いや、そうであるが故の色気を纏っている。
町の男連中が、こぞって彼女の再婚相手を狙っていたり、母子セットで妙なファンクラブがあるのも頷けるくらいの、おっとり系美人だ。ティオとタメを張るほど見事なスタイルを誇っており、体の表面を流れる水滴が実に艶かしい。
そんなタダでさえ魅力的なレミアが、いきなり自分の股の間に出てきたのだ。ミュウのことで頭を悩ますハジメは、うっかり不意をつかれてしまった。レミアは、ハジメの膝に手を掛けて体を支えると、かなり位置的に危ない場所からハジメを見上げている。
しかし、顔のある位置や肉体の放つ色気とは裏腹に、レミアの表情は優しげで、むしろハジメを気遣うような色を宿していた。
「有難うございます。ハジメさん」
「いきなり何だ? 礼を言われるようなことは……」
いきなりお礼を述べたレミアにハジメが訝しそうな表情をする。
「うふふ、娘のためにこんなにも悩んで下さるのですもの……母親としてはお礼の一つも言いたくなります」
「それは……バレバレか。一応、隠していたつもりなんだが」
「あらあら、知らない人はいませんよ? ユエさん達もそれぞれ考えて下さっているようですし……ミュウは本当に素敵な人達と出会えましたね」
レミアは肩越しに振り返って、ミュウのいたずらで水着を剥ぎ取られたシアが、手ブラをしながら必死にミュウを追いかけている姿をみつつ、笑みをこぼす。そして、再度、ハジメに視線を転じると、今度は少し真面目な表情で口を開いた。
「ハジメさん。もう十分です。皆さんは、十分過ぎるほどして下さいました。ですから、どうか悩まずに、すべき事のためにお進み下さい」
「レミア……」
「皆さんと出会って、あの子は大きく成長しました。甘えてばかりだったのに、自分より他の誰かを気遣えるようになった……あの子も分かっています。ハジメさん達が行かなければならないことを……まだまだ幼いですからついつい甘えてしまいますけれど……それでも、一度も“行かないで”とは口にしていないでしょう? あの子も、これ以上、ハジメさん達を引き止めていてはいけないと分かっているのです。だから……」
「……そうか。……幼子に気遣われてちゃあ、世話ないな……わかった。今晩、はっきり告げることにするよ。明日、出発するって」
ミュウの無言の訴えが、行って欲しくないけれど、それを言ってハジメ達を困らせたくないという気遣いの現れだったと気付かされ、片手で目元を覆って天を仰いだハジメは、お別れを告げる決意をする。そんなハジメに、レミアは再び優しげな眼差しを向けた。
「では、今晩はご馳走にしましょう。ハジメさん達のお別れ会ですからね」
「そうだな……期待してるよ」
「うふふ、はい、期待していて下さいね、あ・な・た♡」
「いや、その呼び方は……」
どこかイタズラっぽい笑みを浮かべるレミアに、ハジメはツッコミを入れようとしたが、それはブリザードのような冷たさを含んだ声音により、いつものように遮られた。
「……レミア……いい度胸」
「レミアさん、いつの間に……油断も隙もないよ」
「ふむ、見る角度によっては、ご主人様にご奉仕
「パパー! 朝なのー! 起きるのー!」
海上の町エリセンの一角、とある家の二階で幼子の声が響き渡る。時刻は、そろそろ早朝を過ぎて、日の温かみを感じ始める頃だ。窓から、本日もいい天気になることを予報するように、朝日が燦々と差し込んでいる。
ドスンッ!
「あぁ~?」
そんな朝日に照らされるベッドで爆睡しているのはハジメだ。そして、そんなハジメをパパと呼び、元気な声で起こしに来たのはミュウである。
ミュウは、ベッドの直前で重さを感じさせない見事な跳躍を決めると、そのままパパたるハジメの腹の上に十点満点の着地を決めた。もちろん、足からではない。馬乗りになる形でだ。
まだ四歳の幼子とはいえ、その体重は既に十五、六キロくらいはある。そんな重量が勢い付けて腹部に飛び乗れば、普通の人は呻き声の一つでも出そうなものだが、当然、ハジメは何の痛痒も感じていない。ただ、強制的に起こされたせいで眠たげな呻き声は出たが。
「パパ、起きるの。朝なの。おはようなの」
「……ああ、ミュウか。おはようさん。起きるからペチペチするのは止めてくれ」
ハジメが起きたことが嬉しいのか、ニコニコと笑みをこぼしながら、ミュウは、その小さなモミジのような手でハジメの頬をペチペチと叩く。ハジメは、朝の挨拶をしながら上半身を起こしミュウを抱っこすると、優しくそのエメラルドグリーンの髪を梳いてやった。気持ちよさそうに目を細めるミュウに、ハジメの頬も緩む。何処からどう見ても親子だった。
「……ん……あぅ……ハジメ? ミュウ?」
そんなほのぼのした空気の中に、突如、どこか艶めかしさを感じさせる声音が響いた。ハジメが、そちらに目を向けて少しシーツを捲ると、そこには猫のように丸めた手の甲で目元をコシコシと擦る眠たげな美少女の姿。
寝起きなのに寝癖など全くないウェーブのかかった長い金髪を、窓から差し込む朝日でキラキラと輝かせて、レッドスピネルの如き紅の瞳をシパシパとさせている。ハジメと同じく服を着ていないため、シミ一つない真っ白な肌と、前に垂れ下がった髪の隙間から見える双丘が声音と相まって美しさと共に妖艶さを感じさせた。
「どうして、パパとユエお姉ちゃんは、いつも裸なの?」
ミュウの無邪気な質問は、あくまで“朝起きるとき”という意味だ。決して二人が裸族という意味ではない。
そして、「もしかしてパジャマ持ってないの?」と不思議そうな、あるいは少し可哀想なものを見る目でハジメとユエを交互に見るミュウ。幼く純粋な質問に、「そりゃあ、お前、服は邪魔だろ?」等と、セクハラ紛いの返しなど出来るはずもなく、ハジメは、少し困った表情でユエに助けを求めた。
次第にはっきりしてきた意識で、ハジメの窮状を察したユエは、幼子の無邪気な質問に大人のテンプレで返した。
「……ミュウももっと大きくなれば分かるようになる」
「大きくなったら分かるの?」
「……ん、分かる」
首を傾げるミュウに、ゴリ押しで明確な答えを回避するユエ。ミュウの性教育は母親たるレミアにお任せだ。しかし、「う~ん」とイマイチ納得できなさそうな表情で首を傾げるミュウは、おもむろに振り返ると、とある一点を見つめながら更に無邪気な質問を繰り出して、主にハジメを追い詰めた。
「パパも、ここがおっきくなってるから分かるの? でも、ミュウにはこれないの。ミュウには分からないの?」
そう言って、朝特有の生理現象を起こしているとある場所を、ミュウはその手でペシペシと叩き始めた。大した力ではないとはいえ、デリケートな場所への衝撃にビクンッと震えたハジメは、急いでミュウを抱っこし直し、なるべく“それ”から引き離す。
「ミュウ、あれに触っちゃいけない。いいか。あれは女の子のミュウには無くて当然なんだ。気にしなくていい。あと十年、いや二十年、むしろ一生、何があっても関わっちゃいけないものだ」
至極真面目な顔で阿呆なことを語るハジメ。ミュウは、頭に“?”を浮かべつつも大好きなパパの言うことなのでコクリと素直に頷いた。それに満足気な表情をして、再度、ミュウの髪を手櫛で梳くハジメ。ミュウも、先程までの疑問は忘れたように、その優しい感触を堪能することに集中しだした。
そんなハジメに、隣のユエから何処か面白がるような眼差しが向けられる。その瞳には「過保護」とか「朝から元気」とか「朝からいっとく?」とか、そんな感じのあれこれが含まれているようだった。
それにそっぽを向くハジメ。陽の光で少しずつ暖かさを増していく中、そのほのぼのとした光景は、ミュウが中々ハジメ達を起こして来ない事に焦れたレミアや香織達がなだれ込んで来るまで続いた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ハジメ達が、【メルジーネ海底遺跡】を攻略し、潜水艇を失ったため“竜化”したティオの背に乗ってエリセンまで帰り、再び、町に話題を提供してから六日が経っていた。帰還した日から、ハジメ達は、ずっとレミアとミュウの家に世話になっている。
エリセンという町は、木で編まれた巨大な人口の浮島だ。広大な海そのものが無限の土地となっているので、町中は、通りにしろ建築物にしろ基本的にゆとりのある作りになっている。レミアとミュウの家も、二人暮らしの家にしては十分以上の大きさがあり、ハジメ達五人が寝泊りしても何の不自由も感じない程度には快適な生活空間だった。
そこでハジメ達は、手に入れた神代魔法の習熟と装備品の充実に時間をあてていた。エリセンは海鮮系料理が充実しており、波風も心地よく、中々に居心地のいい場所だったので半分はバカンス気分ではあったが。
ただ、それにしても、六日も滞在しているのは少々骨休めが過ぎると感じるところだ。その理由は、言わずもがな、ミュウである。ミュウを、この先の旅に連れて行くことは出来ない。四歳の何の力もない女の子を、東の果ての大迷宮に連れて行くなどもってのほかだ。
まして、【ハルツィナ樹海】を除く残り二つの大迷宮は更に厄介な場所にある。一つは魔人族の領土にある【シュネー雪原】の【氷結洞窟】。そしてもう一つは、何とあの【神山】なのである。どちらも、大勢力の懐に入り込まねばならないのだ。そんな場所に、ミュウを連れて行くなど絶対に出来ない。
なので、この町でお別れをしなければならないのだが、何となくそれを察しているのか、ハジメ達がその話を出そうとすると、ミュウは決まって超甘えん坊モードになり、ハジメ達に「必殺! 幼女、無言の懇願!」を発動するので中々言い出せずにいた。結局、ズルズルと神代魔法の鍛錬やら新装備の充実化やら、言い訳をしつつ六日も滞在してしまっているのである。
「それでも、いい加減出発しないとな……はぁ、ミュウに何て言うべきか……泣かれるかな。泣かれるよな……はぁ、憂鬱だ」
ハジメは、桟橋に腰掛けて“錬成”により装備やら何やらを作成しながら、憂鬱そうに独り言を呟く。奈落から出たばかりの頃は、この世界の全てをどうでもいいと思っていたのに、今や、幼子とのお別れ一つに頭を悩ませている。そんな現状に、内心、複雑な思いを抱くハジメ。
「恨むぞ、先生……」
この世界の一切合切を切り捨てて、ただ目的のためあらゆる犠牲を厭わないという考えが出来なくなったことに、そんな考えを持つに至ったきっかけたる恩師を思い出して悪態をつくハジメ。しかし、視線の先に、ユエとシア、香織、ティオ、そして彼女達と水中鬼ごっこをして戯れるミュウの溢れる笑顔を見て、言葉とは裏腹に顔には笑みが浮かんでいた。
自分には関係ないと、あの時、ミュウを見捨てていれば、あるいはアンカジを放置していれば、そしてレミアを放って置けば、さっさとミュウと分かれていれば……きっと、彼女達にあの極上の笑顔はなかっただろう。
例え切り捨てていても、ユエ達は不幸だと感じる分けでも笑顔が無くなるわけでもないだろうが、今浮かべるそれとは比べるべくもないのではないだろうか。それはきっと、ここまでのハジメのあり方が“寂しい生き方”ではなかったからに違いない。
海人族の特性を十全に発揮して、チートの権化達から華麗に逃げ回る変則的な鬼ごっこ(ミュウ以外全員鬼役)を全力で楽しんでいるミュウを見ながら、再び、溜息を吐くハジメ。そんなハジメの桟橋から投げ出した両足の間から、突然、人影がザバッと音を立てて現れた。海中から水を滴らせて現れたのは、ミュウの母親であるレミアだ。
レミアは、エメラルドグリーンの長い髪を背中で一本の緩い三つ編みにしており、ライトグリーンの結構際どいビキニを身に付けている。ミュウと再会した当初は、相当やつれていたのだが、現在は、再生魔法という反則級の回復効果により以前の健康体を完全に取り戻しており、一児の母とは思えない、いや、そうであるが故の色気を纏っている。
町の男連中が、こぞって彼女の再婚相手を狙っていたり、母子セットで妙なファンクラブがあるのも頷けるくらいの、おっとり系美人だ。ティオとタメを張るほど見事なスタイルを誇っており、体の表面を流れる水滴が実に艶かしい。
そんなタダでさえ魅力的なレミアが、いきなり自分の股の間に出てきたのだ。ミュウのことで頭を悩ますハジメは、うっかり不意をつかれてしまった。レミアは、ハジメの膝に手を掛けて体を支えると、かなり位置的に危ない場所からハジメを見上げている。
しかし、顔のある位置や肉体の放つ色気とは裏腹に、レミアの表情は優しげで、むしろハジメを気遣うような色を宿していた。
「有難うございます。ハジメさん」
「いきなり何だ? 礼を言われるようなことは……」
いきなりお礼を述べたレミアにハジメが訝しそうな表情をする。
「うふふ、娘のためにこんなにも悩んで下さるのですもの……母親としてはお礼の一つも言いたくなります」
「それは……バレバレか。一応、隠していたつもりなんだが」
「あらあら、知らない人はいませんよ? ユエさん達もそれぞれ考えて下さっているようですし……ミュウは本当に素敵な人達と出会えましたね」
レミアは肩越しに振り返って、ミュウのいたずらで水着を剥ぎ取られたシアが、手ブラをしながら必死にミュウを追いかけている姿をみつつ、笑みをこぼす。そして、再度、ハジメに視線を転じると、今度は少し真面目な表情で口を開いた。
「ハジメさん。もう十分です。皆さんは、十分過ぎるほどして下さいました。ですから、どうか悩まずに、すべき事のためにお進み下さい」
「レミア……」
「皆さんと出会って、あの子は大きく成長しました。甘えてばかりだったのに、自分より他の誰かを気遣えるようになった……あの子も分かっています。ハジメさん達が行かなければならないことを……まだまだ幼いですからついつい甘えてしまいますけれど……それでも、一度も“行かないで”とは口にしていないでしょう? あの子も、これ以上、ハジメさん達を引き止めていてはいけないと分かっているのです。だから……」
「……そうか。……幼子に気遣われてちゃあ、世話ないな……わかった。今晩、はっきり告げることにするよ。明日、出発するって」
ミュウの無言の訴えが、行って欲しくないけれど、それを言ってハジメ達を困らせたくないという気遣いの現れだったと気付かされ、片手で目元を覆って天を仰いだハジメは、お別れを告げる決意をする。そんなハジメに、レミアは再び優しげな眼差しを向けた。
「では、今晩はご馳走にしましょう。ハジメさん達のお別れ会ですからね」
「そうだな……期待してるよ」
「うふふ、はい、期待していて下さいね、あ・な・た♡」
「いや、その呼び方は……」
どこかイタズラっぽい笑みを浮かべるレミアに、ハジメはツッコミを入れようとしたが、それはブリザードのような冷たさを含んだ声音により、いつものように遮られた。
「……レミア……いい度胸」
「レミアさん、いつの間に……油断も隙もないよ」
「ふむ、見る角度によっては、ご主人様にご奉仕
0/5000
娘との誓い「パパー! 朝なのー! 起きるのー!」 海上の町エリセンの一角、とある家の二階で幼子の声が響き渡る。時刻は、そろそろ早朝を過ぎて、日の温かみを感じ始める頃だ。窓から、本日もいい天気になることを予報するように、朝日が燦々と差し込んでいる。ドスンッ!「あぁ~?」 そんな朝日に照らされるベッドで爆睡しているのはハジメだ。そして、そんなハジメをパパと呼び、元気な声で起こしに来たのはミュウである。 ミュウは、ベッドの直前で重さを感じさせない見事な跳躍を決めると、そのままパパたるハジメの腹の上に十点満点の着地を決めた。もちろん、足からではない。馬乗りになる形でだ。 まだ四歳の幼子とはいえ、その体重は既に十五、六キロくらいはある。そんな重量が勢い付けて腹部に飛び乗れば、普通の人は呻き声の一つでも出そうなものだが、当然、ハジメは何の痛痒も感じていない。ただ、強制的に起こされたせいで眠たげな呻き声は出たが。「パパ、起きるの。朝なの。おはようなの」「……ああ、ミュウか。おはようさん。起きるからペチペチするのは止めてくれ」 ハジメが起きたことが嬉しいのか、ニコニコと笑みをこぼしながら、ミュウは、その小さなモミジのような手でハジメの頬をペチペチと叩く。ハジメは、朝の挨拶をしながら上半身を起こしミュウを抱っこすると、優しくそのエメラルドグリーンの髪を梳いてやった。気持ちよさそうに目を細めるミュウに、ハジメの頬も緩む。何処からどう見ても親子だった。「……ん……あぅ……ハジメ? ミュウ?」 そんなほのぼのした空気の中に、突如、どこか艶めかしさを感じさせる声音が響いた。ハジメが、そちらに目を向けて少しシーツを捲ると、そこには猫のように丸めた手の甲で目元をコシコシと擦る眠たげな美少女の姿。 寝起きなのに寝癖など全くないウェーブのかかった長い金髪を、窓から差し込む朝日でキラキラと輝かせて、レッドスピネルの如き紅の瞳をシパシパとさせている。ハジメと同じく服を着ていないため、シミ一つない真っ白な肌と、前に垂れ下がった髪の隙間から見える双丘が声音と相まって美しさと共に妖艶さを感じさせた。「どうして、パパとユエお姉ちゃんは、いつも裸なの?」 ミュウの無邪気な質問は、あくまで“朝起きるとき”という意味だ。決して二人が裸族という意味ではない。 そして、「もしかしてパジャマ持ってないの?」と不思議そうな、あるいは少し可哀想なものを見る目でハジメとユエを交互に見るミュウ。幼く純粋な質問に、「そりゃあ、お前、服は邪魔だろ?」等と、セクハラ紛いの返しなど出来るはずもなく、ハジメは、少し困った表情でユエに助けを求めた。 次第にはっきりしてきた意識で、ハジメの窮状を察したユエは、幼子の無邪気な質問に大人のテンプレで返した。「……ミュウももっと大きくなれば分かるようになる」「大きくなったら分かるの?」「……ん、分かる」 首を傾げるミュウに、ゴリ押しで明確な答えを回避するユエ。ミュウの性教育は母親たるレミアにお任せだ。しかし、「う~ん」とイマイチ納得できなさそうな表情で首を傾げるミュウは、おもむろに振り返ると、とある一点を見つめながら更に無邪気な質問を繰り出して、主にハジメを追い詰めた。「パパも、ここがおっきくなってるから分かるの? でも、ミュウにはこれないの。ミュウには分からないの?」 そう言って、朝特有の生理現象を起こしているとある場所を、ミュウはその手でペシペシと叩き始めた。大した力ではないとはいえ、デリケートな場所への衝撃にビクンッと震えたハジメは、急いでミュウを抱っこし直し、なるべく“それ”から引き離す。「ミュウ、あれに触っちゃいけない。いいか。あれは女の子のミュウには無くて当然なんだ。気にしなくていい。あと十年、いや二十年、むしろ一生、何があっても関わっちゃいけないものだ」 至極真面目な顔で阿呆なことを語るハジメ。ミュウは、頭に“?”を浮かべつつも大好きなパパの言うことなのでコクリと素直に頷いた。それに満足気な表情をして、再度、ミュウの髪を手櫛で梳くハジメ。ミュウも、先程までの疑問は忘れたように、その優しい感触を堪能することに集中しだした。 そんなハジメに、隣のユエから何処か面白がるような眼差しが向けられる。その瞳には「過保護」とか「朝から元気」とか「朝からいっとく?」とか、そんな感じのあれこれが含まれているようだった。 それにそっぽを向くハジメ。陽の光で少しずつ暖かさを増していく中、そのほのぼのとした光景は、ミュウが中々ハジメ達を起こして来ない事に焦れたレミアや香織達がなだれ込んで来るまで続いた。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ハジメ達が、【メルジーネ海底遺跡】を攻略し、潜水艇を失ったため“竜化”したティオの背に乗ってエリセンまで帰り、再び、町に話題を提供してから六日が経っていた。帰還した日から、ハジメ達は、ずっとレミアとミュウの家に世話になっている。 エリセンという町は、木で編まれた巨大な人口の浮島だ。広大な海そのものが無限の土地となっているので、町中は、通りにしろ建築物にしろ基本的にゆとりのある作りになっている。レミアとミュウの家も、二人暮らしの家にしては十分以上の大きさがあり、ハジメ達五人が寝泊りしても何の不自由も感じない程度には快適な生活空間だった。 そこでハジメ達は、手に入れた神代魔法の習熟と装備品の充実に時間をあてていた。エリセンは海鮮系料理が充実しており、波風も心地よく、中々に居心地のいい場所だったので半分はバカンス気分ではあったが。 ただ、それにしても、六日も滞在しているのは少々骨休めが過ぎると感じるところだ。その理由は、言わずもがな、ミュウである。ミュウを、この先の旅に連れて行くことは出来ない。四歳の何の力もない女の子を、東の果ての大迷宮に連れて行くなどもってのほかだ。 まして、【ハルツィナ樹海】を除く残り二つの大迷宮は更に厄介な場所にある。一つは魔人族の領土にある【シュネー雪原】の【氷結洞窟】。そしてもう一つは、何とあの【神山】なのである。どちらも、大勢力の懐に入り込まねばならないのだ。そんな場所に、ミュウを連れて行くなど絶対に出来ない。 なので、この町でお別れをしなければならないのだが、何となくそれを察しているのか、ハジメ達がその話を出そうとすると、ミュウは決まって超甘えん坊モードになり、ハジメ達に「必殺! 幼女、無言の懇願!」を発動するので中々言い出せずにいた。結局、ズルズルと神代魔法の鍛錬やら新装備の充実化やら、言い訳をしつつ六日も滞在してしまっているのである。「それでも、いい加減出発しないとな……はぁ、ミュウに何て言うべきか……泣かれるかな。泣かれるよな……はぁ、憂鬱だ」 ハジメは、桟橋に腰掛けて“錬成”により装備やら何やらを作成しながら、憂鬱そうに独り言を呟く。奈落から出たばかりの頃は、この世界の全てをどうでもいいと思っていたのに、今や、幼子とのお別れ一つに頭を悩ませている。そんな現状に、内心、複雑な思いを抱くハジメ。「恨むぞ、先生……」 この世界の一切合切を切り捨てて、ただ目的のためあらゆる犠牲を厭わないという考えが出来なくなったことに、そんな考えを持つに至ったきっかけたる恩師を思い出して悪態をつくハジメ。しかし、視線の先に、ユエとシア、香織、ティオ、そして彼女達と水中鬼ごっこをして戯れるミュウの溢れる笑顔を見て、言葉とは裏腹に顔には笑みが浮かんでいた。 自分には関係ないと、あの時、ミュウを見捨てていれば、あるいはアンカジを放置していれば、そしてレミアを放って置けば、さっさとミュウと分かれていれば……きっと、彼女達にあの極上の笑顔はなかっただろう。 例え切り捨てていても、ユエ達は不幸だと感じる分けでも笑顔が無くなるわけでもないだろうが、今浮かべるそれとは比べるべくもないのではないだろうか。それはきっと、ここまでのハジメのあり方が“寂しい生き方”ではなかったからに違いない。 海人族の特性を十全に発揮して、チートの権化達から華麗に逃げ回る変則的な鬼ごっこ(ミュウ以外全員鬼役)を全力で楽しんでいるミュウを見ながら、再び、溜息を吐くハジメ。そんなハジメの桟橋から投げ出した両足の間から、突然、人影がザバッと音を立てて現れた。海中から水を滴らせて現れたのは、ミュウの母親であるレミアだ。 レミアは、エメラルドグリーンの長い髪を背中で一本の緩い三つ編みにしており、ライトグリーンの結構際どいビキニを身に付けている。ミュウと再会した当初は、相当やつれていたのだが、現在は、再生魔法という反則級の回復効果により以前の健康体を完全に取り戻しており、一児の母とは思えない、いや、そうであるが故の色気を纏っている。 町の男連中が、こぞって彼女の再婚相手を狙っていたり、母子セットで妙なファンクラブがあるのも頷けるくらいの、おっとり系美人だ。ティオとタメを張るほど見事なスタイルを誇っており、体の表面を流れる水滴が実に艶かしい。 そんなタダでさえ魅力的なレミアが、いきなり自分の股の間に出てきたのだ。ミュウのことで頭を悩ますハジメは、うっかり不意をつかれてしまった。レミアは、ハジメの膝に手を掛けて体を支えると、かなり位置的に危ない場所からハジメを見上げている。
しかし、顔のある位置や肉体の放つ色気とは裏腹に、レミアの表情は優しげで、むしろハジメを気遣うような色を宿していた。
「有難うございます。ハジメさん」
「いきなり何だ? 礼を言われるようなことは……」
いきなりお礼を述べたレミアにハジメが訝しそうな表情をする。
「うふふ、娘のためにこんなにも悩んで下さるのですもの……母親としてはお礼の一つも言いたくなります」
「それは……バレバレか。一応、隠していたつもりなんだが」
「あらあら、知らない人はいませんよ? ユエさん達もそれぞれ考えて下さっているようですし……ミュウは本当に素敵な人達と出会えましたね」
レミアは肩越しに振り返って、ミュウのいたずらで水着を剥ぎ取られたシアが、手ブラをしながら必死にミュウを追いかけている姿をみつつ、笑みをこぼす。そして、再度、ハジメに視線を転じると、今度は少し真面目な表情で口を開いた。
「ハジメさん。もう十分です。皆さんは、十分過ぎるほどして下さいました。ですから、どうか悩まずに、すべき事のためにお進み下さい」
「レミア……」
「皆さんと出会って、あの子は大きく成長しました。甘えてばかりだったのに、自分より他の誰かを気遣えるようになった……あの子も分かっています。ハジメさん達が行かなければならないことを……まだまだ幼いですからついつい甘えてしまいますけれど……それでも、一度も“行かないで”とは口にしていないでしょう? あの子も、これ以上、ハジメさん達を引き止めていてはいけないと分かっているのです。だから……」
「……そうか。……幼子に気遣われてちゃあ、世話ないな……わかった。今晩、はっきり告げることにするよ。明日、出発するって」
ミュウの無言の訴えが、行って欲しくないけれど、それを言ってハジメ達を困らせたくないという気遣いの現れだったと気付かされ、片手で目元を覆って天を仰いだハジメは、お別れを告げる決意をする。そんなハジメに、レミアは再び優しげな眼差しを向けた。
「では、今晩はご馳走にしましょう。ハジメさん達のお別れ会ですからね」
「そうだな……期待してるよ」
「うふふ、はい、期待していて下さいね、あ・な・た♡」
「いや、その呼び方は……」
どこかイタズラっぽい笑みを浮かべるレミアに、ハジメはツッコミを入れようとしたが、それはブリザードのような冷たさを含んだ声音により、いつものように遮られた。
「……レミア……いい度胸」
「レミアさん、いつの間に……油断も隙もないよ」
「ふむ、見る角度によっては、ご主人様にご奉仕
しかし、顔のある位置や肉体の放つ色気とは裏腹に、レミアの表情は優しげで、むしろハジメを気遣うような色を宿していた。
「有難うございます。ハジメさん」
「いきなり何だ? 礼を言われるようなことは……」
いきなりお礼を述べたレミアにハジメが訝しそうな表情をする。
「うふふ、娘のためにこんなにも悩んで下さるのですもの……母親としてはお礼の一つも言いたくなります」
「それは……バレバレか。一応、隠していたつもりなんだが」
「あらあら、知らない人はいませんよ? ユエさん達もそれぞれ考えて下さっているようですし……ミュウは本当に素敵な人達と出会えましたね」
レミアは肩越しに振り返って、ミュウのいたずらで水着を剥ぎ取られたシアが、手ブラをしながら必死にミュウを追いかけている姿をみつつ、笑みをこぼす。そして、再度、ハジメに視線を転じると、今度は少し真面目な表情で口を開いた。
「ハジメさん。もう十分です。皆さんは、十分過ぎるほどして下さいました。ですから、どうか悩まずに、すべき事のためにお進み下さい」
「レミア……」
「皆さんと出会って、あの子は大きく成長しました。甘えてばかりだったのに、自分より他の誰かを気遣えるようになった……あの子も分かっています。ハジメさん達が行かなければならないことを……まだまだ幼いですからついつい甘えてしまいますけれど……それでも、一度も“行かないで”とは口にしていないでしょう? あの子も、これ以上、ハジメさん達を引き止めていてはいけないと分かっているのです。だから……」
「……そうか。……幼子に気遣われてちゃあ、世話ないな……わかった。今晩、はっきり告げることにするよ。明日、出発するって」
ミュウの無言の訴えが、行って欲しくないけれど、それを言ってハジメ達を困らせたくないという気遣いの現れだったと気付かされ、片手で目元を覆って天を仰いだハジメは、お別れを告げる決意をする。そんなハジメに、レミアは再び優しげな眼差しを向けた。
「では、今晩はご馳走にしましょう。ハジメさん達のお別れ会ですからね」
「そうだな……期待してるよ」
「うふふ、はい、期待していて下さいね、あ・な・た♡」
「いや、その呼び方は……」
どこかイタズラっぽい笑みを浮かべるレミアに、ハジメはツッコミを入れようとしたが、それはブリザードのような冷たさを含んだ声音により、いつものように遮られた。
「……レミア……いい度胸」
「レミアさん、いつの間に……油断も隙もないよ」
「ふむ、見る角度によっては、ご主人様にご奉仕
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
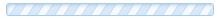
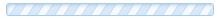
Bahasa lainnya
Dukungan alat penerjemahan: Afrikans, Albania, Amhara, Arab, Armenia, Azerbaijan, Bahasa Indonesia, Basque, Belanda, Belarussia, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Burma, Cebuano, Ceko, Chichewa, China, Cina Tradisional, Denmark, Deteksi bahasa, Esperanto, Estonia, Farsi, Finlandia, Frisia, Gaelig, Gaelik Skotlandia, Galisia, Georgia, Gujarati, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Ibrani, Igbo, Inggris, Islan, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Kannada, Katala, Kazak, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Klingon, Korea, Korsika, Kreol Haiti, Kroat, Kurdi, Laos, Latin, Latvia, Lituania, Luksemburg, Magyar, Makedonia, Malagasi, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Melayu, Mongol, Nepal, Norsk, Odia (Oriya), Pashto, Polandia, Portugis, Prancis, Punjabi, Rumania, Rusia, Samoa, Serb, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovakia, Slovenia, Somali, Spanyol, Sunda, Swahili, Swensk, Tagalog, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turki, Turkmen, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnam, Wales, Xhosa, Yiddi, Yoruba, Yunani, Zulu, Bahasa terjemahan.
- Sangat enak
- Senin dudaklarön çok güzel
- 4. Apakah dengan diberlakukan Syariat Is
- 15. Jadi apakah dengan dikuatkuasakan qa
- Kesayangan
- Karena pakai pemerah bibir
- Iya, anda mau?
- Tamam canım anladöm
- 1. Bagaimana pemahaman anda tentang gend
- اللهم في يوم الجمعة افرح قلوبنا واغسل اح
- Aku begitu kangen pada mu semua nya takk
- Apakah payu daramu besar
- Kesayangan saya
- How to riset YouTube Apple id password
- Nelerden hoşlnıyosun aşkım
- Amirku sayang
- Kerja dimana?
- attitudinal barriers . attitudinal barri
- Ingin aku memejam kan mata ini sesaat ag
- Selamat ulang tahun sayang,,semoga panja
- Ingin aku memejam kan mata ini sesaat ag
- Selamat ulang tahun sayang,,semoga panja
- Biasa aja
- Sdg nama ayah saya

