- Teks
- Sejarah
「――どうしても、行くというのか?」 ふいに、ガーフィールの耳朶を聞き
「――どうしても、行くというのか?」
ふいに、ガーフィールの耳朶を聞き慣れた声が打った。
しかし、それはこの場で聞こえるはずのない声だった。
なぜならそれは、この場でガーフィールに干渉できるものの声ではなく、この場でガーフィールが干渉できるものの声でもなかったからだ。
「ええ、行きます。リューズ様には、ご迷惑をおかけしてしまうんですけど」
「別にそんなこと気にしやせん。問題は、この子らの気持ちの方じゃ」
交わされる言葉は、聞き慣れた家族のものと、聞き慣れない家族のものだ。
渋い顔をしたリューズの口が動き、向き合う母の口が動き、音が滑り込んでくる。
記憶の中になかったはずの母の声を、ガーフィールは初めて耳にした。
「――――」
息を呑み、ガーフィールは目の前の光景に意識を奪われる。
母は腕の中のガーフィールを愛おしむように見つめて、その体を揺すってあやしていた。その母を見上げて、スカートの裾を掴むフレデリカが声を絞る。
「お、お母様……わ、わたくし……わたくしは」
「ごめんね、フーちゃん。あなたに、たくさんの心配をかけちゃうわよね」
「いいんです。わたくしは、大丈夫。でも、ガーフが可哀想で……」
「一緒に連れてったら、お母さんドジだもの。きっと、ガーちゃんが大変な思いをするわ。フーちゃん、お母さんの子なのにしっかりしてるから、お願いね」
寂しがりながらも、母を見送る言葉を投げかけるフレデリカ。
母親が『聖域』を離れることを、姉が肯定していたことをガーフィールは初めて知る。リューズも、震えるフレデリカの肩を抱いて、その意思を尊重する様子だ。
「ガーちゃん。お母さん、行ってくるわね」
呼びかけながら、母はガーフィールを持ち上げる。
掲げられたガーフィールは、母の決意も知らぬ顔で無邪気に笑っていた。母はそのガーフィールを抱き寄せると、額にそっと口づけする。
その場所は、今はガーフィールの白い傷跡があるのと同じ場所で。
「きっと、あなたのお父さんを連れて戻るから。それまで、待っていて」
「――――ッ!」
慈愛に満ちた瞳と、思いやりに溢れた言葉。
離れ難い思い出を手放さないために、母は何度も何度も、ガーフィールに口づけする。
そうしてからようやく、幼いガーフィールをリューズへ手渡した。
しっかりとガーフィールの体を抱き、頷き合うリューズと母。母はそれからフレデリカと抱き合い、ガーフィールと同じように愛娘の額にも口づけの雨を注ぐ。
「――は、ァ。あ、ああァ……あァァ……ッ」
それを目にしながら、ガーフィールはいつの間にかその場に膝をついていた。
自分が、何を見ているのかわからない。
こんな光景は知らない。こんな光景は、見た覚えがない。
まだ小さかった頃、何もわかっていなかった頃、過去に挑んだとき、ガーフィールが見たのはもっと救いようのない、身を切られるような絶望の記憶だったはずだ。
ガーフィールはそんな記憶であっても、そんな風に打ち捨てられたような思いを噛みしめた記憶であっても、大切なものであると信じ込んで頑なさを育ててきた。
それが、これまでの日々が、鬱屈と惨めさを覆い隠すように張ってきた虚勢が、剥がれ落ちて、崩れ落ちて、まったく別のものへと塗り替えられる。
なんなのだ、この記憶は。
母は、自分と姉を捨てて、自分の幸せだけを追い求めて出ていったのではないのか。邪魔な自分たちを人生から切り捨てて、自分の道を歩もうとしていたのではないのか。
これでは、あべこべではないか。
母は自分と姉を捨てて出ていった。だからこそ、ガーフィールは『ガーフィール・ティンゼル』という存在を、強固に形作ることができていたのだ。
それが見当違いのまやかしだったと気付いたとき、強固な防壁は脆い土壁に変わり、ガーフィールの世界は足下から崩壊する。
もはや真っ直ぐに立っていることすらできないガーフィールの前で、過去の自分たち家族の別れが終わりを迎える。
存分に別れを惜しんだ母は、フレデリカとガーフィールに最後に触れて、リューズに全てを任せると鞄一つを持って森の外へ向かう。
途中で、何度も立ち止まる。振り返り、見送りの手を振るフレデリカを。リューズに手を持たれて、母を見送る手を振らされるガーフィールを見て、手を振り返す。
また、気を取り直して歩き出す。立ち止まってしまう。振り返り、手を振る。
そんなことを何度も、何度も何度も繰り返して、母は森の外へと――。
「――な、ァ!?」
その母の後を追いかけようと、立ち上がりかけた視界がふいに歪んだ。
世界の輪郭がぼやけるのは、ガーフィールの瞳に涙の雫が溜まっていることばかりが理由ではない。もっとはっきりと、明快な理由で世界は曖昧になりかけている。
視界の端から白い光に包まれて、森が消失していくのだ。
まるで世界の終焉――展開されていた物語の意図せぬ終わりに、ガーフィールは背後に佇んでいる魔女を振り返り、叫ぶ。
「なんでだ! なんで、こんなッとこで終わろうとする! まだ、肝心なとこが……」
「いいや、終わりだよ。これ以上を見る必要はない。夢の終わりを認めたのは、ワタシじゃない君の方だ。おめでとう、ガーフィール。君は、君の過去を塗り替えた」
「何を……ッ!? ッざッけんじゃァねェ! 俺様が一番、どうにかしなきゃァなんねェのはこっから先で……!」
「この先を見ることは必要ないし、仮に君がこの先に起きる何かを思い描いていたとしても、そこに君が干渉する余地はない」
「ァ――」
それは、過去は変えられないという魔女の答えなのか。
血の気の上っていたガーフィールの顔色が変わり、立ち上がりかけた膝が落ちる。
母の、本当の気持ちがわかったのに。
この場を去った、母のその後の運命は変わらないということなのか。
母は、ガーフィールやフレデリカのために、父を捜しに『聖域』を立った。しかしその旅は、始まってすぐに潰えることになる。母の命と、一緒に。
――救いようのない記憶が、もっと救われない結果に落ち込んだだけではないのか。
絶望に、絶望を上塗りするだけだった記憶が、希望が、絶望に塗り潰される記憶に切り替わっただけではないのか。これで、自分の何を変えろというのだ。
「お母様は、わたくしのことも、ガーフのことも、愛してくれていましたわ」
弾かれたように顔を上げて、ガーフィールは正面を見る。
跪く自分を見下ろして、幼い姿の姉がそう言っていた。瞳は、ガーフィールを見ている。見えないはずの、干渉できないはずの過去が、干渉してくる。
「家族のために、お母様は『聖域』を出た。そのことに、不満があるというの?」
「ふざ、ふざッけんな! 愛されてたから、なんだってんだ! よ、余計な記憶がぶら下がっただけじゃァねェか。俺様ァ……!」
「愛されていない方が、気が楽だったですものね」
幼いフレデリカが、反論するガーフィールを小馬鹿にするように言い捨てる。
身長差は文字通り子どもと大人ほどもある。なのに、姉はまるで背丈のことなど気にも留めずに、相手は手のかかる弟だとでも言いたげな顔で真っ向からぶつかってくる。
「一方通行の愛情だと思っていれば、自分のことを正当化できる」
「違う……ッ!」
「愛していて、愛されていて……そうだったと思い知ってしまったら、外に飛び出していかなかった自分を、『聖域』にこもった自分を正当化できなくなりますものね」
「違うッ! 違う違うッ! なんにも知らねェくせに……母さんが、どうなったか!」
「――知らないはず、ないでしょう」
怒りに任せて叫ぼうとしたガーフィールに、それは殴られるような衝撃を与えた。
眼前のフレデリカは表情を消して、感情を堪えるように自分を見ている。
――今、姉はなんと言ったのか?
「知らないはずがないでしょう。仮にお母様が『聖域』の外に出て、すぐに何か不幸に見舞われたとしたら……それを、聞かされていないはずがないでしょう」
「だ……ッたら、なんで……!?」
「それをあなたに伝えられるはずがないことも、わかるでしょう。ガーフ。もう、あなたは幼い子どもじゃないのですから」
母に何が起きたのか、フレデリカは知っていた。
そして、幼いガーフィールにそれが話せなかった理由は、ガーフィールにもわかる。
誰がまだ幼い少年に、母親の残酷な最期のことなど伝えられる。
墓所で『試練』を垣間見ることがなければ、ガーフィールは知らないままだったはずだ。そうならなかったのは、そうさせないための多くの思いやりを踏み越えたからだ。
「お母様に愛されていたこと、本当は覚えていたでしょう」
「…………」
ふいに、ガーフィールの耳朶を聞き慣れた声が打った。
しかし、それはこの場で聞こえるはずのない声だった。
なぜならそれは、この場でガーフィールに干渉できるものの声ではなく、この場でガーフィールが干渉できるものの声でもなかったからだ。
「ええ、行きます。リューズ様には、ご迷惑をおかけしてしまうんですけど」
「別にそんなこと気にしやせん。問題は、この子らの気持ちの方じゃ」
交わされる言葉は、聞き慣れた家族のものと、聞き慣れない家族のものだ。
渋い顔をしたリューズの口が動き、向き合う母の口が動き、音が滑り込んでくる。
記憶の中になかったはずの母の声を、ガーフィールは初めて耳にした。
「――――」
息を呑み、ガーフィールは目の前の光景に意識を奪われる。
母は腕の中のガーフィールを愛おしむように見つめて、その体を揺すってあやしていた。その母を見上げて、スカートの裾を掴むフレデリカが声を絞る。
「お、お母様……わ、わたくし……わたくしは」
「ごめんね、フーちゃん。あなたに、たくさんの心配をかけちゃうわよね」
「いいんです。わたくしは、大丈夫。でも、ガーフが可哀想で……」
「一緒に連れてったら、お母さんドジだもの。きっと、ガーちゃんが大変な思いをするわ。フーちゃん、お母さんの子なのにしっかりしてるから、お願いね」
寂しがりながらも、母を見送る言葉を投げかけるフレデリカ。
母親が『聖域』を離れることを、姉が肯定していたことをガーフィールは初めて知る。リューズも、震えるフレデリカの肩を抱いて、その意思を尊重する様子だ。
「ガーちゃん。お母さん、行ってくるわね」
呼びかけながら、母はガーフィールを持ち上げる。
掲げられたガーフィールは、母の決意も知らぬ顔で無邪気に笑っていた。母はそのガーフィールを抱き寄せると、額にそっと口づけする。
その場所は、今はガーフィールの白い傷跡があるのと同じ場所で。
「きっと、あなたのお父さんを連れて戻るから。それまで、待っていて」
「――――ッ!」
慈愛に満ちた瞳と、思いやりに溢れた言葉。
離れ難い思い出を手放さないために、母は何度も何度も、ガーフィールに口づけする。
そうしてからようやく、幼いガーフィールをリューズへ手渡した。
しっかりとガーフィールの体を抱き、頷き合うリューズと母。母はそれからフレデリカと抱き合い、ガーフィールと同じように愛娘の額にも口づけの雨を注ぐ。
「――は、ァ。あ、ああァ……あァァ……ッ」
それを目にしながら、ガーフィールはいつの間にかその場に膝をついていた。
自分が、何を見ているのかわからない。
こんな光景は知らない。こんな光景は、見た覚えがない。
まだ小さかった頃、何もわかっていなかった頃、過去に挑んだとき、ガーフィールが見たのはもっと救いようのない、身を切られるような絶望の記憶だったはずだ。
ガーフィールはそんな記憶であっても、そんな風に打ち捨てられたような思いを噛みしめた記憶であっても、大切なものであると信じ込んで頑なさを育ててきた。
それが、これまでの日々が、鬱屈と惨めさを覆い隠すように張ってきた虚勢が、剥がれ落ちて、崩れ落ちて、まったく別のものへと塗り替えられる。
なんなのだ、この記憶は。
母は、自分と姉を捨てて、自分の幸せだけを追い求めて出ていったのではないのか。邪魔な自分たちを人生から切り捨てて、自分の道を歩もうとしていたのではないのか。
これでは、あべこべではないか。
母は自分と姉を捨てて出ていった。だからこそ、ガーフィールは『ガーフィール・ティンゼル』という存在を、強固に形作ることができていたのだ。
それが見当違いのまやかしだったと気付いたとき、強固な防壁は脆い土壁に変わり、ガーフィールの世界は足下から崩壊する。
もはや真っ直ぐに立っていることすらできないガーフィールの前で、過去の自分たち家族の別れが終わりを迎える。
存分に別れを惜しんだ母は、フレデリカとガーフィールに最後に触れて、リューズに全てを任せると鞄一つを持って森の外へ向かう。
途中で、何度も立ち止まる。振り返り、見送りの手を振るフレデリカを。リューズに手を持たれて、母を見送る手を振らされるガーフィールを見て、手を振り返す。
また、気を取り直して歩き出す。立ち止まってしまう。振り返り、手を振る。
そんなことを何度も、何度も何度も繰り返して、母は森の外へと――。
「――な、ァ!?」
その母の後を追いかけようと、立ち上がりかけた視界がふいに歪んだ。
世界の輪郭がぼやけるのは、ガーフィールの瞳に涙の雫が溜まっていることばかりが理由ではない。もっとはっきりと、明快な理由で世界は曖昧になりかけている。
視界の端から白い光に包まれて、森が消失していくのだ。
まるで世界の終焉――展開されていた物語の意図せぬ終わりに、ガーフィールは背後に佇んでいる魔女を振り返り、叫ぶ。
「なんでだ! なんで、こんなッとこで終わろうとする! まだ、肝心なとこが……」
「いいや、終わりだよ。これ以上を見る必要はない。夢の終わりを認めたのは、ワタシじゃない君の方だ。おめでとう、ガーフィール。君は、君の過去を塗り替えた」
「何を……ッ!? ッざッけんじゃァねェ! 俺様が一番、どうにかしなきゃァなんねェのはこっから先で……!」
「この先を見ることは必要ないし、仮に君がこの先に起きる何かを思い描いていたとしても、そこに君が干渉する余地はない」
「ァ――」
それは、過去は変えられないという魔女の答えなのか。
血の気の上っていたガーフィールの顔色が変わり、立ち上がりかけた膝が落ちる。
母の、本当の気持ちがわかったのに。
この場を去った、母のその後の運命は変わらないということなのか。
母は、ガーフィールやフレデリカのために、父を捜しに『聖域』を立った。しかしその旅は、始まってすぐに潰えることになる。母の命と、一緒に。
――救いようのない記憶が、もっと救われない結果に落ち込んだだけではないのか。
絶望に、絶望を上塗りするだけだった記憶が、希望が、絶望に塗り潰される記憶に切り替わっただけではないのか。これで、自分の何を変えろというのだ。
「お母様は、わたくしのことも、ガーフのことも、愛してくれていましたわ」
弾かれたように顔を上げて、ガーフィールは正面を見る。
跪く自分を見下ろして、幼い姿の姉がそう言っていた。瞳は、ガーフィールを見ている。見えないはずの、干渉できないはずの過去が、干渉してくる。
「家族のために、お母様は『聖域』を出た。そのことに、不満があるというの?」
「ふざ、ふざッけんな! 愛されてたから、なんだってんだ! よ、余計な記憶がぶら下がっただけじゃァねェか。俺様ァ……!」
「愛されていない方が、気が楽だったですものね」
幼いフレデリカが、反論するガーフィールを小馬鹿にするように言い捨てる。
身長差は文字通り子どもと大人ほどもある。なのに、姉はまるで背丈のことなど気にも留めずに、相手は手のかかる弟だとでも言いたげな顔で真っ向からぶつかってくる。
「一方通行の愛情だと思っていれば、自分のことを正当化できる」
「違う……ッ!」
「愛していて、愛されていて……そうだったと思い知ってしまったら、外に飛び出していかなかった自分を、『聖域』にこもった自分を正当化できなくなりますものね」
「違うッ! 違う違うッ! なんにも知らねェくせに……母さんが、どうなったか!」
「――知らないはず、ないでしょう」
怒りに任せて叫ぼうとしたガーフィールに、それは殴られるような衝撃を与えた。
眼前のフレデリカは表情を消して、感情を堪えるように自分を見ている。
――今、姉はなんと言ったのか?
「知らないはずがないでしょう。仮にお母様が『聖域』の外に出て、すぐに何か不幸に見舞われたとしたら……それを、聞かされていないはずがないでしょう」
「だ……ッたら、なんで……!?」
「それをあなたに伝えられるはずがないことも、わかるでしょう。ガーフ。もう、あなたは幼い子どもじゃないのですから」
母に何が起きたのか、フレデリカは知っていた。
そして、幼いガーフィールにそれが話せなかった理由は、ガーフィールにもわかる。
誰がまだ幼い少年に、母親の残酷な最期のことなど伝えられる。
墓所で『試練』を垣間見ることがなければ、ガーフィールは知らないままだったはずだ。そうならなかったのは、そうさせないための多くの思いやりを踏み越えたからだ。
「お母様に愛されていたこと、本当は覚えていたでしょう」
「…………」
0/5000
「――どうしても、行くというのか?」 ふいに、ガーフィールの耳朶を聞き慣れた声が打った。 しかし、それはこの場で聞こえるはずのない声だった。 なぜならそれは、この場でガーフィールに干渉できるものの声ではなく、この場でガーフィールが干渉できるものの声でもなかったからだ。「ええ、行きます。リューズ様には、ご迷惑をおかけしてしまうんですけど」「別にそんなこと気にしやせん。問題は、この子らの気持ちの方じゃ」 交わされる言葉は、聞き慣れた家族のものと、聞き慣れない家族のものだ。 渋い顔をしたリューズの口が動き、向き合う母の口が動き、音が滑り込んでくる。 記憶の中になかったはずの母の声を、ガーフィールは初めて耳にした。「――――」 息を呑み、ガーフィールは目の前の光景に意識を奪われる。 母は腕の中のガーフィールを愛おしむように見つめて、その体を揺すってあやしていた。その母を見上げて、スカートの裾を掴むフレデリカが声を絞る。「お、お母様……わ、わたくし……わたくしは」「ごめんね、フーちゃん。あなたに、たくさんの心配をかけちゃうわよね」「いいんです。わたくしは、大丈夫。でも、ガーフが可哀想で……」「一緒に連れてったら、お母さんドジだもの。きっと、ガーちゃんが大変な思いをするわ。フーちゃん、お母さんの子なのにしっかりしてるから、お願いね」 寂しがりながらも、母を見送る言葉を投げかけるフレデリカ。 母親が『聖域』を離れることを、姉が肯定していたことをガーフィールは初めて知る。リューズも、震えるフレデリカの肩を抱いて、その意思を尊重する様子だ。「ガーちゃん。お母さん、行ってくるわね」 呼びかけながら、母はガーフィールを持ち上げる。 掲げられたガーフィールは、母の決意も知らぬ顔で無邪気に笑っていた。母はそのガーフィールを抱き寄せると、額にそっと口づけする。 その場所は、今はガーフィールの白い傷跡があるのと同じ場所で。「きっと、あなたのお父さんを連れて戻るから。それまで、待っていて」「――――ッ!」 慈愛に満ちた瞳と、思いやりに溢れた言葉。 離れ難い思い出を手放さないために、母は何度も何度も、ガーフィールに口づけする。 そうしてからようやく、幼いガーフィールをリューズへ手渡した。 しっかりとガーフィールの体を抱き、頷き合うリューズと母。母はそれからフレデリカと抱き合い、ガーフィールと同じように愛娘の額にも口づけの雨を注ぐ。「――は、ァ。あ、ああァ……あァァ……ッ」 それを目にしながら、ガーフィールはいつの間にかその場に膝をついていた。 自分が、何を見ているのかわからない。 こんな光景は知らない。こんな光景は、見た覚えがない。 まだ小さかった頃、何もわかっていなかった頃、過去に挑んだとき、ガーフィールが見たのはもっと救いようのない、身を切られるような絶望の記憶だったはずだ。 ガーフィールはそんな記憶であっても、そんな風に打ち捨てられたような思いを噛みしめた記憶であっても、大切なものであると信じ込んで頑なさを育ててきた。 それが、これまでの日々が、鬱屈と惨めさを覆い隠すように張ってきた虚勢が、剥がれ落ちて、崩れ落ちて、まったく別のものへと塗り替えられる。 なんなのだ、この記憶は。 母は、自分と姉を捨てて、自分の幸せだけを追い求めて出ていったのではないのか。邪魔な自分たちを人生から切り捨てて、自分の道を歩もうとしていたのではないのか。 これでは、あべこべではないか。 母は自分と姉を捨てて出ていった。だからこそ、ガーフィールは『ガーフィール・ティンゼル』という存在を、強固に形作ることができていたのだ。 それが見当違いのまやかしだったと気付いたとき、強固な防壁は脆い土壁に変わり、ガーフィールの世界は足下から崩壊する。 もはや真っ直ぐに立っていることすらできないガーフィールの前で、過去の自分たち家族の別れが終わりを迎える。 存分に別れを惜しんだ母は、フレデリカとガーフィールに最後に触れて、リューズに全てを任せると鞄一つを持って森の外へ向かう。 途中で、何度も立ち止まる。振り返り、見送りの手を振るフレデリカを。リューズに手を持たれて、母を見送る手を振らされるガーフィールを見て、手を振り返す。 また、気を取り直して歩き出す。立ち止まってしまう。振り返り、手を振る。 そんなことを何度も、何度も何度も繰り返して、母は森の外へと――。「――な、ァ!?」 その母の後を追いかけようと、立ち上がりかけた視界がふいに歪んだ。 世界の輪郭がぼやけるのは、ガーフィールの瞳に涙の雫が溜まっていることばかりが理由ではない。もっとはっきりと、明快な理由で世界は曖昧になりかけている。 視界の端から白い光に包まれて、森が消失していくのだ。 まるで世界の終焉――展開されていた物語の意図せぬ終わりに、ガーフィールは背後に佇んでいる魔女を振り返り、叫ぶ。「なんでだ! なんで、こんなッとこで終わろうとする! まだ、肝心なとこが……」「いいや、終わりだよ。これ以上を見る必要はない。夢の終わりを認めたのは、ワタシじゃない君の方だ。おめでとう、ガーフィール。君は、君の過去を塗り替えた」「何を……ッ!? ッざッけんじゃァねェ! 俺様が一番、どうにかしなきゃァなんねェのはこっから先で……!」「この先を見ることは必要ないし、仮に君がこの先に起きる何かを思い描いていたとしても、そこに君が干渉する余地はない」「ァ――」 それは、過去は変えられないという魔女の答えなのか。 血の気の上っていたガーフィールの顔色が変わり、立ち上がりかけた膝が落ちる。 母の、本当の気持ちがわかったのに。 この場を去った、母のその後の運命は変わらないということなのか。 母は、ガーフィールやフレデリカのために、父を捜しに『聖域』を立った。しかしその旅は、始まってすぐに潰えることになる。母の命と、一緒に。 ――救いようのない記憶が、もっと救われない結果に落ち込んだだけではないのか。 絶望に、絶望を上塗りするだけだった記憶が、希望が、絶望に塗り潰される記憶に切り替わっただけではないのか。これで、自分の何を変えろというのだ。
「お母様は、わたくしのことも、ガーフのことも、愛してくれていましたわ」
弾かれたように顔を上げて、ガーフィールは正面を見る。
跪く自分を見下ろして、幼い姿の姉がそう言っていた。瞳は、ガーフィールを見ている。見えないはずの、干渉できないはずの過去が、干渉してくる。
「家族のために、お母様は『聖域』を出た。そのことに、不満があるというの?」
「ふざ、ふざッけんな! 愛されてたから、なんだってんだ! よ、余計な記憶がぶら下がっただけじゃァねェか。俺様ァ……!」
「愛されていない方が、気が楽だったですものね」
幼いフレデリカが、反論するガーフィールを小馬鹿にするように言い捨てる。
身長差は文字通り子どもと大人ほどもある。なのに、姉はまるで背丈のことなど気にも留めずに、相手は手のかかる弟だとでも言いたげな顔で真っ向からぶつかってくる。
「一方通行の愛情だと思っていれば、自分のことを正当化できる」
「違う……ッ!」
「愛していて、愛されていて……そうだったと思い知ってしまったら、外に飛び出していかなかった自分を、『聖域』にこもった自分を正当化できなくなりますものね」
「違うッ! 違う違うッ! なんにも知らねェくせに……母さんが、どうなったか!」
「――知らないはず、ないでしょう」
怒りに任せて叫ぼうとしたガーフィールに、それは殴られるような衝撃を与えた。
眼前のフレデリカは表情を消して、感情を堪えるように自分を見ている。
――今、姉はなんと言ったのか?
「知らないはずがないでしょう。仮にお母様が『聖域』の外に出て、すぐに何か不幸に見舞われたとしたら……それを、聞かされていないはずがないでしょう」
「だ……ッたら、なんで……!?」
「それをあなたに伝えられるはずがないことも、わかるでしょう。ガーフ。もう、あなたは幼い子どもじゃないのですから」
母に何が起きたのか、フレデリカは知っていた。
そして、幼いガーフィールにそれが話せなかった理由は、ガーフィールにもわかる。
誰がまだ幼い少年に、母親の残酷な最期のことなど伝えられる。
墓所で『試練』を垣間見ることがなければ、ガーフィールは知らないままだったはずだ。そうならなかったのは、そうさせないための多くの思いやりを踏み越えたからだ。
「お母様に愛されていたこと、本当は覚えていたでしょう」
「…………」
「お母様は、わたくしのことも、ガーフのことも、愛してくれていましたわ」
弾かれたように顔を上げて、ガーフィールは正面を見る。
跪く自分を見下ろして、幼い姿の姉がそう言っていた。瞳は、ガーフィールを見ている。見えないはずの、干渉できないはずの過去が、干渉してくる。
「家族のために、お母様は『聖域』を出た。そのことに、不満があるというの?」
「ふざ、ふざッけんな! 愛されてたから、なんだってんだ! よ、余計な記憶がぶら下がっただけじゃァねェか。俺様ァ……!」
「愛されていない方が、気が楽だったですものね」
幼いフレデリカが、反論するガーフィールを小馬鹿にするように言い捨てる。
身長差は文字通り子どもと大人ほどもある。なのに、姉はまるで背丈のことなど気にも留めずに、相手は手のかかる弟だとでも言いたげな顔で真っ向からぶつかってくる。
「一方通行の愛情だと思っていれば、自分のことを正当化できる」
「違う……ッ!」
「愛していて、愛されていて……そうだったと思い知ってしまったら、外に飛び出していかなかった自分を、『聖域』にこもった自分を正当化できなくなりますものね」
「違うッ! 違う違うッ! なんにも知らねェくせに……母さんが、どうなったか!」
「――知らないはず、ないでしょう」
怒りに任せて叫ぼうとしたガーフィールに、それは殴られるような衝撃を与えた。
眼前のフレデリカは表情を消して、感情を堪えるように自分を見ている。
――今、姉はなんと言ったのか?
「知らないはずがないでしょう。仮にお母様が『聖域』の外に出て、すぐに何か不幸に見舞われたとしたら……それを、聞かされていないはずがないでしょう」
「だ……ッたら、なんで……!?」
「それをあなたに伝えられるはずがないことも、わかるでしょう。ガーフ。もう、あなたは幼い子どもじゃないのですから」
母に何が起きたのか、フレデリカは知っていた。
そして、幼いガーフィールにそれが話せなかった理由は、ガーフィールにもわかる。
誰がまだ幼い少年に、母親の残酷な最期のことなど伝えられる。
墓所で『試練』を垣間見ることがなければ、ガーフィールは知らないままだったはずだ。そうならなかったのは、そうさせないための多くの思いやりを踏み越えたからだ。
「お母様に愛されていたこと、本当は覚えていたでしょう」
「…………」
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
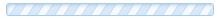
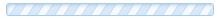
Bahasa lainnya
Dukungan alat penerjemahan: Afrikans, Albania, Amhara, Arab, Armenia, Azerbaijan, Bahasa Indonesia, Basque, Belanda, Belarussia, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Burma, Cebuano, Ceko, Chichewa, China, Cina Tradisional, Denmark, Deteksi bahasa, Esperanto, Estonia, Farsi, Finlandia, Frisia, Gaelig, Gaelik Skotlandia, Galisia, Georgia, Gujarati, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Ibrani, Igbo, Inggris, Islan, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Kannada, Katala, Kazak, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Klingon, Korea, Korsika, Kreol Haiti, Kroat, Kurdi, Laos, Latin, Latvia, Lituania, Luksemburg, Magyar, Makedonia, Malagasi, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Melayu, Mongol, Nepal, Norsk, Odia (Oriya), Pashto, Polandia, Portugis, Prancis, Punjabi, Rumania, Rusia, Samoa, Serb, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovakia, Slovenia, Somali, Spanyol, Sunda, Swahili, Swensk, Tagalog, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turki, Turkmen, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnam, Wales, Xhosa, Yiddi, Yoruba, Yunani, Zulu, Bahasa terjemahan.
- my baby honey
- 3.2 Grammatical Analysis of the TextThe
- そして、そんなスバルの祈りはむなしく届かない。「ついた……」 石造りの通路を抜け
- Getwellson
- Apa anda dari malaysia akan ke indonesia
- Go away
- Cute olivia Olivia is a young gril in my
- Stay with me
- متى يمكن لنا اللعنة تماماy
- Saya inggin mencium mu cinta ku.
- Kamu jangan bosan berteman dengan aku da
- Cans
- Sabar
- (critical, discourse, analysis
- @mehmetay Fotograf icin @frhtsirin e tes
- Mention
- Waktu Indonesia lebih cepat dibanding tu
- in some instances the public agency may
- Kamu jangan bosan berteman dengan aku da
- I dont care
- Ada penyambutan untuk mahasiswa baru
- そして、そんなスバルの祈りはむなしく届かない。「ついた……」 石造りの通路を抜け
- You send messages
- Telah pergi

